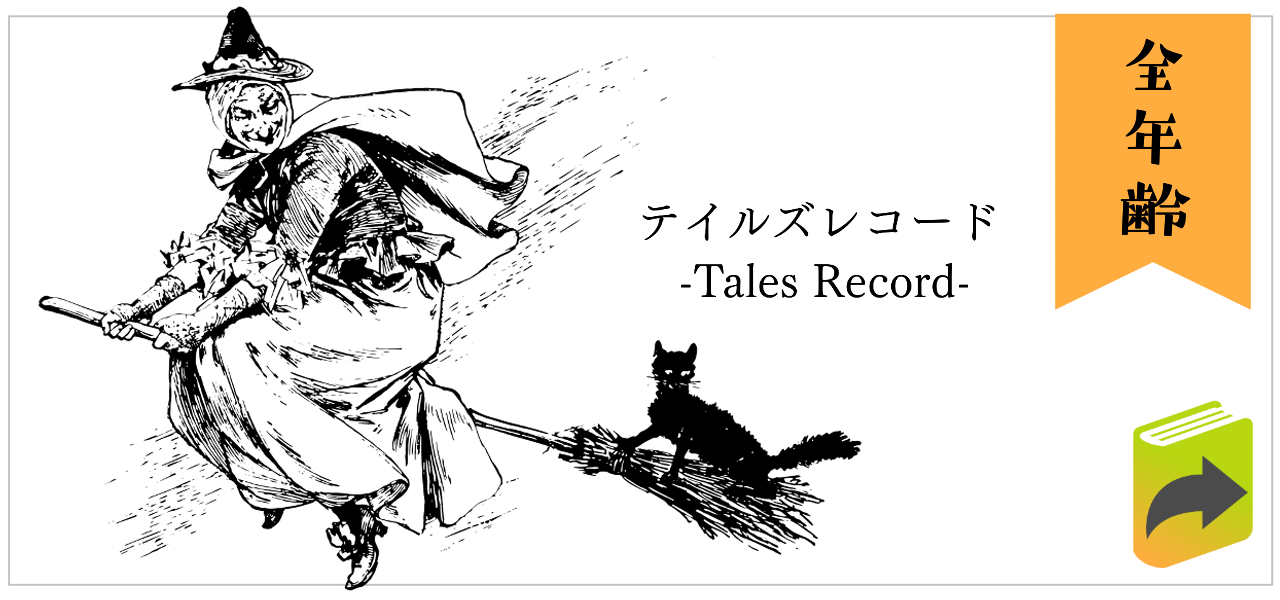密瓶(かたられる宝石たちの秘密より)
この作品は、作曲していただきオリジナル曲としても発表されています。
2020年5月発行「かたられる宝石たちの秘密」に収録されました。
密瓶
古い図書館のように時代の息を感じる不思議な空間では、年季の入った木製の窓枠から室内に差し込む光の道筋を辿っているのか、粒子がキラキラと舞っていた。それをホコリなどという単純な表現で済ませたくはない。いつだってそこには、人間が目にすること出来ない不思議な存在が潜んでいて、また興味深そうにこちら側を見ているというものである。
「はぁ」
いや、訂正しよう。
幻想的な粒子の円舞ではなく、溜息を吐いた少年サリドが、もう何年も使い古されたソファーに身を投げ出したせいで舞ったホコリである、と。
そしてこれは、私、ミーシェ・アルチェの五十日目の日記である。
記念すべき五十日目を私は朝から楽しみにしていた。意気揚々と、この西棟の端にある秘密の部屋に来ることだけを考えて、退屈な朝の時間をやり過ごしたと言ってもいい。面白くない授業、眠気を誘うチュイア教授の声が今もまだ頭の中をこだましている。あの書き取りは意味があるのか、あの教科書を丸暗記させるような呪文に耐えた私を褒めてあげたい。だが、まあ。なにはともあれ、私は今、ここにいる。
なんて幸せな時間。
記念すべき五十日目に何を呟こうかと密瓶を手にして考えていた。そうしたら、彼が来たのだ。私の幸せの時間を破壊しにきた悪魔め。ああ、いけない。心の声は穏やかでいなくては。この日記に余計な感情は不要。私が、ミーシェ・アルチェという人物が、いかに崇高で有能な人物であるかを記すために始めた日記に、無粋な感情を閉じ込めるわけにはいかない。
「ふあぁあ」
大きな欠伸は私ではない。
彼、サリドが初めてここに来たのは一週間前。入学して三か月がたった頃。彼はまた複数の女子に追い掛け回されたのか、はたまた昨夜、いけない妄想のせいで眠れなかったのか。逃げ込みに来たのか、惰眠を貪りにきたのか、どちらにしろ私にとっては迷惑なことこの上ない。
チラリと、ソファーに横たわり窓枠から差し込むキラキラとしたホコリを無言で眺め続ける男へ視線を向ける。サリド・マグイット。学園内の女子は皆、一度は彼に恋するというが、見目はたしかに群を抜いて良い。おまけに頭もいいときた。先日発表された魔術家養成コースの成績一位の欄にはサリドの名前があったことを私は記憶している。
「なんだよ?」
不機嫌な視線が窓枠からこちらを向いた。
突然の流れだったので思わず目が合ってしまったが、すぐにそらしたので万事問題はないだろう。危ない危ない。頭が良くて、見た目が良い。そういう人種には深く関わらない方が身のためなのだ。私とは住む世界が違う。彼にこの密瓶という素晴らしい世界を理解できる繊細さはないだろう。
この古い図書館のように神聖かつ静寂に満ちたこの場所で永遠に静かな学園生活を送るためには、彼のような有名人と関わってはいけないと本能が悟っている。本音を漏らすのであれば、彼がここに来ることさえ私は望んでいない。今はまだ誰もが、この部屋を気味悪がってサリドをここまで探しに来ないが、彼がここに足を運んでくる以上、いつこの聖域が侵されるとも知れない。
「無視、ねぇ」
これ見よがしな視線が痛い。一体、私が何をしたというのだ。
こっちを見ないで欲しい。私が視線をそらしたのだからサリドも視線をどこかへやればいいものを、一体なぜ見つめられているのかがわからない。
ドキドキと心臓がおかしくなる。
サリドがこの秘密の部屋に来るようになってから、私の心臓は時々こうしておかしくなる。変に早くなり、熱が出るのだ。体に変調をきたすなど冗談じゃない。サリドに関わってはいけない。私の本能は告げている。
「はぁ、だっり」
無視。それに越したことはない。
こちらを見つめていた深い紫色の瞳がつまらなさそうにまた窓枠に向く。そうだ、ずっとそのまま大人しくしていろと、私の心がうんうんと首を強く縦に振った。
魔術家養成コースのある名門フィスタント学園は気が遠くなるほど広い校舎を持ち、特に西棟の校舎はその大抵は何のために使われているかわからない教室で埋め尽くされている。その中でもとりわけ人が足を踏み入れたがらない場所に、この部屋は存在していた。通称「亡霊室」夜な夜な不気味な声が聞こえる噂のせいでそう呼ばれるようになったらしいが、正式名称は「密霊室(みつれいしつ)」まあ、通称名と大差ないのも仕方がない。
だってここは、様々な言葉が詰め込まれた無数の瓶を展示している特別な部屋。
私だけの秘密の部屋。
宝石よりも美しく、価値ある歴史に触れることが出来る至高の場所。
「ふぁあ」
なぜ、こんな素敵な部屋でサリドが欠伸をこぼせるのかはわからない。
特異魔法で磨かれた透明なガラス瓶に詰め込んだものは、風化が遅れていつまでも高い保存状態のままでいるという。つまり、この小瓶に詰められた言葉たちは時代を超えて過去から未来へと旅するひとつの転生装置とも言えるだろう。
例えば、私の後ろにある棚の一番上の棚、丁度真ん中から左に二つ目の小さな瓶。
それは二百年前に、雇い主の領主に叶わぬ恋をした貧しい少女の心が詰め込まれている。初めてあれに触れた時は、そのあまりの切なさと甘酸っぱさと息苦しさに、恋とはこれほどまでに心を締め付け、痺れさせる効果があるのかと震えたものだった。
次に、四段目、一番右端にあるあの大きな瓶。
少し曇っているがあれはよくない。
五十年前、ここの売店でパンを売っていたおばさんが、二十年間も溜めた愚痴が詰まっている。おかげで今、偉そうに授業をしているチュイア教授が昔は小柄でいじめられていたという事実を知ることが出来たが、得られた情報はその程度だった。
つまり、大きな瓶だからといって、沢山の言葉が詰まっているからといって、必ずしもそれが良質だとは限らない。
それがこの密霊室にある瓶の魅力であり、一日中引きこもっていても飽きない場所だと言うことを証明している。瓶は誰が何の目的で集めたのか、この部屋には何万、いや何千万という数の瓶が保存されている。
今日はどの瓶にしようか。
なんて、一日の中にある密かな楽しみをこの男は知らない。ずいぶん人生を損しているなと思う。教えてやる必要や義理はどこにもないが、邪魔はしてくれるなと私はサリドに再び視線を向けた。
「っ」
なぜ、こちらを見つめているのかはわからない。
先ほど視線を外したくせに、なぜ再び私を見つめているのか、私にはわからない。
盛大な欠伸をこぼしていたくせに、サリドがじっと私を見つめている理由は、想像すらも難しい理解の範疇を超えていた。
「なあ、お前。ミーシェ・アルチェだよな」
「は、え、なっ」
「同じクラスのやつの名前くらい覚えるだろ」
「いや、私、あの」
「なんで、毎日亡霊室にいんの?」
純粋な疑問が私の胸を締め付ける。なぜって決まっているだろう。
「真意に触れられる場所だからよ」
誰も聞いていない、誰にも知られない。そういう秘密の言葉は、普段演じている人物とは違う本来の姿で現れる。封じられ、閉じ込められた言葉は、そのときの感情の熱を保ったまま瓶の中で永年を眠り続けている。
その魅力を知らない人は実に多い。
学園一モテる男、サリドさえ。ここに足を運びながらその魅力に気が付かないのだ。沢山の思いや言葉が密接し、ひしめき合うこの場所で欠伸をこぼすくらいの神経の持ち主なのだから無理もないだろう。
「私にとっては宝石よりも価値のある特別なものなの」
ふんっと鼻を鳴らして私はサリドに、それ以上近付くなという警戒の念を送る。この程度の魔法は、名門フィスタント学園の魔術家養成コースに入学する者なら誰にだってできる。
ところが、サリドには何の問題もないらしい。
「へぇ」
いつの間に背後に来たのか、瓶を両手で持って立っていた私の背中越しにサリドの息が吹きかかる。
「ミーシェはその瓶に何の言葉を詰め込んだわけ?」
「ッ?!」
慌てて振り返ったのも無理はない。魔法の瓶は言葉を詰め込むための特別な瓶。透明の中身は空っぽではなく、普段とは違う人の本性が詰め込まれていく。今、こうして心の中で喋ってきた沢山の言葉が詰め込まれていく。
入学して三か月。
入学後、五十日目にこの部屋を見つけたその日からずっと、溜めて来た日記のような瓶を背後の男に触れられるわけにはいかない。
「だめっ」
勢いよく振り返ったその瞬間、瓶に腕を伸ばして前かがみになった美麗な顔が私の頬に髪を落とした。
これは事故だ。
柔らかな唇の感触など、事故以外の何だというのか。
両手の中に持ったままの魔法の瓶はこの瞬間の出来事すらも、私の意思に反して記憶してしまったことだろう。
ああ、なんたる不運。
最悪だ。
(完)

Tales Recordとは
当サイトの「日常の中にほんの少しの非日常を」を基盤に作られた個人短編集です。「今日もこの世界のどこかで生きている」をキャッチコピーにしています。なさそうであり、ありそうでない。そんな狭間のお話たちの試し読みができます