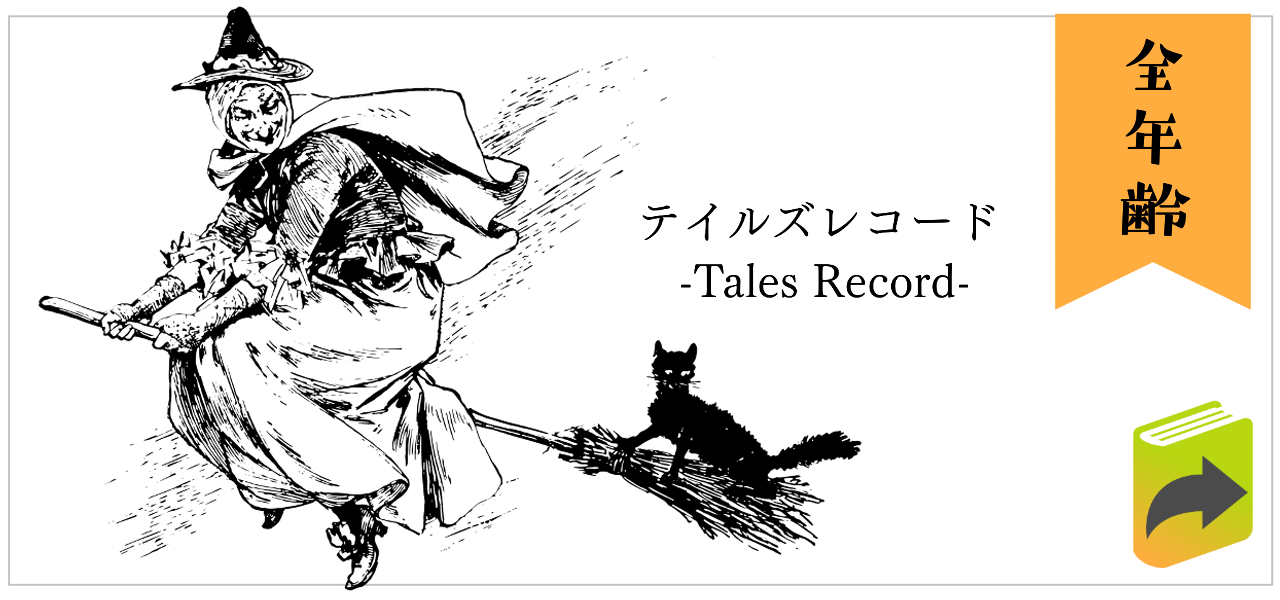双璧の勾玉(かたられる宝石たちの秘密より)
この作品は、2020年5月発行「かたられる宝石たちの秘密」に収録されました。
双璧の勾玉
カシャンと、中が空洞で出来た簡素な飾りが音を立てて美晴の手から落ちた。元来は鈴としてその役割を果たしていただろう道具も寂れたのか、乾いた音しか響かせない。深い森の奥にある、忘れられた祭壇。幼いころに夢に見た場所は、腐敗が進んだ建物の重圧に崩れて、今にも塵に返ってしまいそうだった。
「ごめんなさい」
都会にでも遊びに行くような場違いな恰好は、落とした鈴の上に重なり落ちる。
膝をついた美晴の声が夕暮れの差し込む深い森の中で、静かな悲しみをこぼしていた。
「ごめんなさい」
目の前に転がる鈴を手に取って、美晴は橙色の差し込む祭壇の中心で顔を覆う。ギシっと足元がイヤな音をたてたが、もともといつ崩れてもおかしくない場所。今更、怖いだとか、危ないだとか、そういう感情はどこにもなかった。あるのはただ悲愴だけ。
膝をついた美晴の視線の先には、小さな子どもがかぶっていただろう麦わら帽子。
捨てていかれたのか、忘れていったのか、真っ赤なリボンがついた帽子だけが腐敗した世界の中で、異様なほど形を崩さずそこにある。虫に食われることもなく、当時の形を保ったまま、今もまだそこにある。
「ごめんなさい」
茜色の陽光は、大事にされていた年月を伝えるように美晴の前を照らし続ける。
自然と込み上げる後悔の念と涙の先に触れなければ、美晴の夢は永遠に闇と共に眠るだろう。
* * * * * *
「あなた、変な耳」
さかのぼること十五年前。今は記憶にも遠いその日は、まだ神社はそこで神社として存在していた。四歳の夏。過疎の村は高齢化が進み、最後の住民である祖母の引退と共にその村の上を高速道路が走ることになっていた。そのため、遺品整理も含めて数日の滞在を余儀なくされた美晴の両親は、まだ幼い美晴をつれてある夏をその村で過ごすことにした。
螺奈土村。
かつては稲作で栄えたらしいが、利便性が悪く、人は増えずに離れていった。美晴の祖母だけが、山の奥にある神社を管理していたこともあり、死ぬまで村を離れることを拒んでいた。
「あなた、変な服」
近くで遊んでいなさいと言われたにも関わらず、どうしてたどり着いたのか、美晴は気づけば神社の境内に足を踏み入れていた。小さな子どもが一人で歩くにしては険しい山道。薄桃のワンピースに黄色のサンダル。赤いリボンがついた麦わら帽子をかぶった女の子が、ふらっと訪れるには説明しがたい現象。
それでも、美晴は誰に連れて行ってもらうわけでもなく、その日、その神社にいた。
そして、見たのだ。真っ白な衣装に身を包み、大きな耳を生やした小さな少年を。
「あなた、聞こえないの?」
好奇心の塊といえばそれまでだが、無垢というのは恐ろしい。大人であれば警戒するその姿を何も思わないのか、美晴は社の前、四角い石に座るその少年に向かって語りかけていた。
「ねぇ、あなた名前は?」
少年はずっと同じ姿勢をしたまま無言を貫いている。森の奥深く、参拝者を失った神社に白い少年。年は美晴と大して変わらなく見えるが、その体に生えた耳や尻尾は冗談でつけているようには見えない。その証拠に、美晴の声に耳が動き、尻尾が左右に揺れている。
「あのね、わたし、みはるっていうの」
ついに美晴はその少年が座る台に両手をついて、その顔を覗き込んだ。
下から真っ直ぐ、キラキラと何か新しいおもちゃでも見つめるような無垢な瞳を拒むことは難しい。聞いてもいないのに、美晴の字はどう書くとか、四歳になったとか、お父さんとお母さんは忙しいだとかを嬉々として喋っている。そしてついに「どうして喋れないのに、お耳としっぽが揺れてるの?」と、真顔で首を傾げられれば無視のしようがない。
「はぁ」
我慢比べの敗北を溜息に混ぜたのか、白い少年は姿勢を崩すように美晴の顔を覗き込んだ。
「お前なぁ、ちょっとは黙っていられないわけ?」
「お前じゃない、美晴」
そう言い返すように少年の瞳を覗き込んだ美晴が小さく息を呑む。一体どうしたのかと少年の白い耳が疑問符を浮かべて左に傾いたところで、キャーっと美晴の声が黄色の声援を叫んでいた。
「あなたの目、青くてキラキラでとってもきれい。素敵、素敵、王子様みたい」
「ちょっ、うわぁ」
「近くで見てもキラキラしてる」
少年の顔を両手でつかんで自分の方へ引き寄せた美晴の声が弾んでいる。無邪気な力ほど強力なものはない。台から滑り落ちないようにするだけで精一杯なのか、美晴を映した青い瞳は「美晴、うるさいって言われるだろ?」と冷たい言葉を投げていた。途端にパッと美晴の両手が少年の顔を解放する。
ようやく自分の顔が帰って来たと、少年は頬をさすりながら、急におとなしくなった美晴へと視線を下げた。
「うるさいって言われる」
しゅんとうなだれた美晴の様子に胸が痛む。先ほどまでの勢いはどうしたのかと狼狽えたその時、クスクスと笑う声が美晴の横に降り立った。
「あーあ、雪螺がそんな言い方するから」
「いや、俺は別に」
そんなつもりじゃと、言葉を濁した台の上の少年を見上げるように美晴の隣に立っていたのは、同じく耳と尻尾を生やした白い少年。鏡に映したようにそっくりなその容姿は、美晴の顔を何度も左右に往復させた。
「せつら?」
どちらがどうなのか判別が難しい。
「こいつの名前は雪螺。で、僕の名前が焔螺」
「せつら、ほむら」
台の上が雪螺、横にいるのが焔螺。ずっと同じ位置にいてくれれば認識が容易いが、ようやく名前を飲み込めたところで雪螺が台から降りてしまったのだから困惑する。
「きみは美晴ちゃん、だっけ?」
「そう、美晴。あ、ほむらの目もキラキラしてる」
見分ける場所がひとつあった。
「赤くてキラキラでとても綺麗」
赤が焔螺。
青が雪螺。
目を見れば間違えようのない二人に、美晴の顔が喜びに代わる。何度も瞳を見つめながら嬉しそうに名前を復唱する美晴に、いつしか焔螺と雪螺も笑って美晴の名前を呼んでいた。
「そうだ美晴ちゃん。とっておきの踊りをみせてあげる」
「おい、焔螺」
「いいじゃん、雪螺。もうこれが最後かもしれないんだし」
腕を引いた焔螺に導かれるように、美晴は本殿に足を踏み入れる。そこは何もない広い空間で、艶やかな木の板が敷かれただけの簡素な部屋だった。その中心で舞い始めた焔螺と雪螺に、赤と青の閃光が輪を描く。それはあまりに幻想的で、幼い美晴にとって魔法といえるような不思議な光景を映していた。
「美晴も一緒に踊る」
いてもたってもいられなくなった声が輪の中に飛び込んでいく。
最初は驚いた様子を見せた焔螺と雪螺は、でたらめに舞う美晴の手をとって、円を描くように何度も踊りを繰り返した。
不思議と聞こえる音楽があるとすれば、今まさに美晴はその中にいただろう。
「楽しいね、三人でいるとすごく楽しい」
踊りつかれた三人は息を切らしたように輪になって寝転がる。
天井には二匹の狐が中心にある白い球体を守るように舞う姿が描かれていた。円になるように、お互いの尻尾と額を近づけて、赤と青が白に唇を寄せている。
「ねぇ、雪螺と焔螺は楽しい?」
「楽しい、かな」
「だな」
天井の絵を見たついでに視線だけで二人の位置を確認した美晴は満足そうに微笑む。
「ずっとこの時間が続いたらいいのに」
それは本心で吐き出した言葉だった。
「美晴ちゃんはそろそろ家に帰らないといけないね」
「やだ」
「ヤダって、このまま永遠に帰れなくなったらそれこそイヤだろ?」
「やだ、まだ一緒に遊ぶ。雪螺と焔螺と一緒にいたい」
「そうは言ってもなぁ、俺らここから離れられねぇし」
「困ったね」
「昔のような力があれば美晴一人、里に返すくらいわけないんだけどな」
「まあね」
ひそひそと囁き合う雪螺と焔螺の声が聞こえないのか、んーと難しい顔で膨れていた美晴が、突如思い出したようにパンっと両手を叩く。
「あ、そうだ。いいこと考えた。せつら、ほむら、美晴が螺奈様になったら二人とずっと遊べるよ」
大きな耳のせいで人よりも聴覚が発達しているのだろう。雪螺も焔螺も悶絶するように耳を抑えてバタバタと声にならない足を響かせている。けれど、満足そうな美晴にそれは関係ない。
「おばあちゃんがね、螺奈様は美晴がいいねって」
ごろんと寝返りを打って、美晴は二匹の狐に向かって「そうでしょう」と言わんばかりの笑みを浮かべていた。
「螺奈様って意味わかって言ってるのか?」
「おひめさまだよ」
「力をはく奪された神を愛するモノ好きの間違いだろ」
「えー、いいじゃない。僕、美晴ちゃんだったらなれると思うな」
「焔螺、またお前は適当に」
美晴に習って寝返りを打った三人は、頬杖を突きながらお互いに顔を見合わせる。にこにこと機嫌のいい美晴に怪訝な顔をした雪螺だが、焔螺は何か妙案が浮かんだのか悪戯に口を歪めて座りなおすと、服の裾から小さな手で持つには少し大きな玉飾りを取り出した。
「じゃあ、美晴ちゃんにこれをあげる」
「なに?」
「美晴ちゃんが忘れなければ」
「忘れそうだな」
「美晴は、忘れないよ?」
「どうだか」
「ほら、雪螺も。どうせこのまま消えてなくなるなら、美晴ちゃんに託すのもありでしょ」
「ったく、仕方ない。美晴、手出せ」
向かい合うように配置された真っ白な二つの勾玉。赤と青の宝石が埋め込まれているのか、その中央には白い鈴が二色の色をのぞかせながら軽やかな音を立てている。
「きれい、美晴がもらってもいいの?」
「美晴ちゃんだからもらってほしいんだよ」
「大事にしろよ」
「ありがとう、焔螺、雪螺」
「美晴、この玉飾りを失くさないで」
「絶対ここに、戻って来ると約束しろ」
「うん、約束する。美晴、絶対ここに帰ってくるよ」
* * * * * *
小さなころ。夢は螺奈様になることだった。
なぜそんな夢を持ったのか。祖母の影響だと母は笑っていたが、美晴も例外なく年齢を重ねるにつれて夢は変動していた。
いつの間にか忘れていた夢。四歳の夏、神社の境内でひとり眠っていた美晴を発見したのは父親だったが、救助隊が出るほどの騒ぎになったらしいことを今でも酒の席でからかわれる。
どうやって神社まで行ったのかと聞かれても、実際よく覚えていなかった。
何をしていたのかと聞かれても、本当に何をしたのか覚えていなかった。ただ眠りながらも、身に覚えのない玉飾りをずっと握りしめていたらしい。
「ごめんなさい」
思い出したのは、つい二日前のこと。春から大学生になるのにあわせて一人暮らしを始めた美晴は、その荷物整理をしていた過程で例の玉飾りを見つけた。
入れた覚えはない。
不気味なほど変色したその存在を手にした瞬間、今までどうして忘れていたのかと思えるほど、繊細に記憶がよみがえってきた。
「ごめんなさい」
記憶を頼りに電車とバスを乗り継ぎ、やってきた懐かしい場所。まだバスが通っていたとこが唯一の救いだったが、神社のある場所に足を踏み入れた途端、美晴の中で思い出は絶望の色に染まった。
記憶の中では古いながらも整頓され、形を保っていたはずの社殿は管理者を失って壁を消している。腐った柱に支えられた屋根は傾き、石の台座は欠けて、枯れ葉や藻が覆っている。
あまりの変貌ぶりに言葉が出ない。
着の身着のまま出てきた自分が恨めしい、掃除道具も何もない。忘れられた悲しみだけが雰囲気の中に潜んでいた。
「せつら、ほむら?」
両手で握りしめていた玉飾りがギシリとさび付いた音を響かせる。
ふらふらと石がむき出しになった段差を登り、かつて二人の少年と踊った場所の中心まで足を運んで、美晴はその手に握っていた鈴を足元に落としてしまった。
「ごめんなさい」
四歳の自分がかぶっていた麦わら帽子だけが、腐敗した世界の中で色を保ち続けている。
「雪螺、焔螺」
玉飾りに口付けるように美晴の声が静かに名を呼ぶ。
記憶の中の小さな神様。彼らの住む場所が廃墟同然の様子を見せる限り、あの日に交わした約束を守れるとは到底思えなかった。
「雪螺、焔螺、もう一度会いたい」
太陽が傾いていく。茜色は何も変わらずそこに差すのに、会いたい二人の面影だけがどこにもないようで、たまらないほど寂しかった。悲しかった。忘れていたのは自分なのに、それを払しょくできる希望を探していた。
「来るのが遅い」
「え?」
これは夢だろうか。橙色の後光の中ではその影の顔がよく見えない。
「まあまあ、雪螺。美晴ちゃんとの記念すべき再会の第一声がそれってどうなの?」
「ちょ、はっ、え?」
大きな耳、ふさふさのしっぽ。記憶の中では小さな少年だったはずだが、どう見ても影の大きさは成人男性ほどの背丈と厚みをもって存在感を放っている。
一言で理解が追い付かない。
「美晴ちゃん、霊力高いの気づいてなかった?」
焔螺の声をした赤い瞳の美しい狐男が視線を合わせるようにしゃがんでくる。端整な顔。狐につままれたというのは、こういうときに使う言葉だったか。
「ずっと長い間、傍にいて力を分けてもらってたけど、いやぁ、十分な力をもらったとはいえ、契約の場所じゃないと出られないのが難点だよね」
そういう彼が視線を流した先で、今度は青い瞳を持った狐男が疲れたように首を回していた。
「ああ、狭くて死ぬかと思った」
「あはは、死なないよ。だって僕たち神様だもん」
「待って、理解が追い付かないんだけど」
たまらず叫んだ美晴を二つの視線が悠然と見つめる。
「だって、麦わら帽子は?」
指を差した場所では、たしかに麦わら帽子が静かに鎮座し続けていた。けれど、先ほど違って時が流れたのか、徐々に風化し始めて見えるのは気のせいではないだろう。
「ここで契約をしましたよって印にきみの持ち物が必要だって言ったら、美晴ちゃんがこれにするって言ったの覚えてないの?」
「ま、覚えてないだろ。実際、玉飾りの扱い雑だったしな」
よいしょっと軽々しく手を引かれて立たされると、ますます二人の大きさに困惑する。頭ひとつ、いや、ふたつ。耳があるせいで余計に高く見える長身と、見惚れるほどの肉体美に息を呑みたいところだが、人間離れしたその存在を改めて肉眼で確認するとこれは夢だと思いたくもなる。
「わかった。感動とか感傷とか、どこかに吹っ飛んでいったけど。なんだか終わりよければすべてよしってことで」
パンっと両手を叩けば、夢になると思ったけれど、そうでもないらしい。
現実として目の前で動く、摩訶不思議な正体が美麗な顔のままニコリと悪戯に微笑んでいる。
「美晴ちゃん、なにか大事なこと忘れてない?」
「え?」
「螺奈様になってくれるんだよね?」
「螺奈様、ああ。あの村に伝わるお姫様のこと。太古の昔、双子の神は悪戯好きが徒となって封印された。その封印を解き放つことが出来るのは螺奈様だけって話を、私、なんでかお姫様だと思って憧れてたんだよね」
「姫じゃなくて嫁だよ、嫁」
「・・・・・え?」
「求婚したのはお前だから責任もてよ」
「は、い?」
「そういうわけで、これからもよろしくね」
茜色の差し込む廃墟で似つかわしくない光景が照らし出される。最後の役目を終えたようにバキッと屋根が傾きに斜線を描いたが、それが何だというのだろう。白い耳としっぽを揺らした赤と青の瞳の間で、引きつった顔の美晴がひとり。決定した未来の行方に、声にならない心情を叫んでいた。(完)

Tales Recordとは
当サイトの「日常の中にほんの少しの非日常を」を基盤に作られた個人短編集です。「今日もこの世界のどこかで生きている」をキャッチコピーにしています。なさそうであり、ありそうでない。そんな狭間のお話たちの試し読みができます