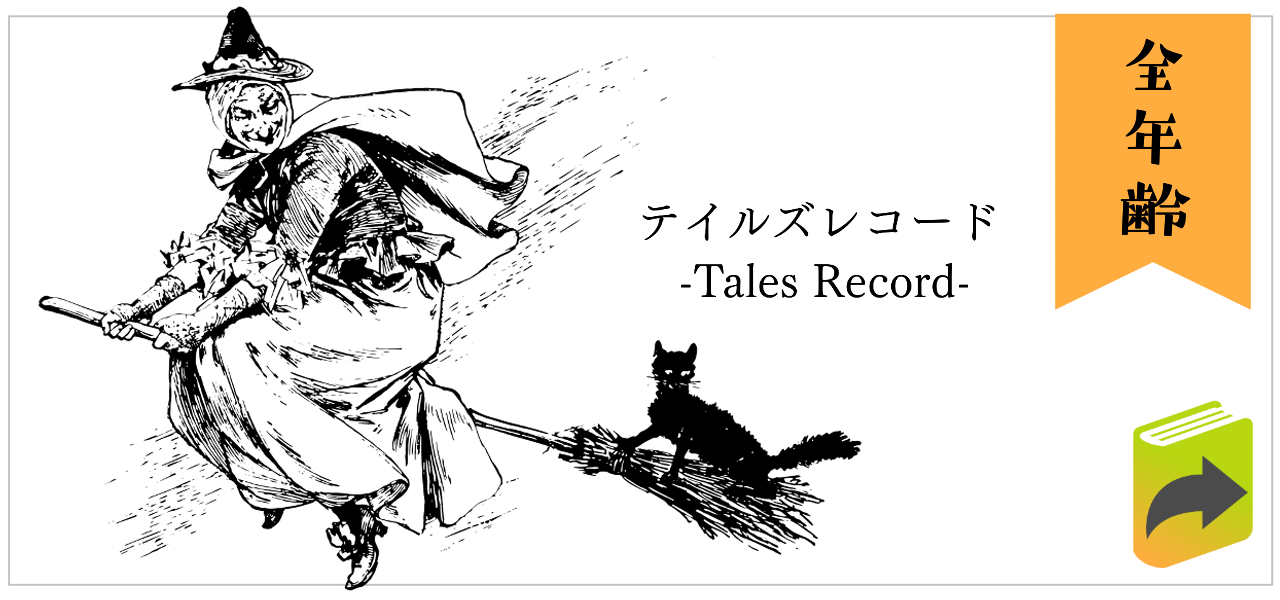百年待ちの魔女(ありふれた魔女たちの日常より)
この作品は、過去にYoutubeにて朗読、小説家になろうにて短編掲載をおこなっております。
2018年9月発行「ありふれた魔女たちの日常」に収録されました。
百年待ちの魔女
森の奥深くにある、その小さな店は不思議なもので溢れていた。
山猫の尻尾で作られた帽子、ラピスラズリを削った笛、竜の鱗で出来た簪、異国から流れ着いた瓶詰めの船。それらが乱雑に並べられた棚に囲まれて、この店の中央には主人が座る椅子がポツンとひとつ飾られていた。
誰もいない。
時間を忘れそうな穏やかな匂いが店内には漂っている。
その時「いらっしゃいませ」と控えめな声が聞こえてきた。
「魔女だ」
少年は、声になりかけた言葉を飲み込んで、部屋につながる扉から入ってきた店主を見つめていた。
内心の緊張が現実になってしまったのだろうか、深い海の底のような雰囲気を携えて、魔女はゆっくりと中央に飾られた椅子へ向かっている。途中にあるものなど、まるで興味がないように。透き通る青い空色の目で、真っ黒な夜を着て、煌めく月のような柔らかな髪が揺れている。
そして椅子に腰かけるなり、鈴のような声で魔女は一言「いやよ」と笑った。
「あ、あの」
言葉を発するよりも早くに、心臓がドキドキと早鐘を打っている。そんな少年がまだ何かを伝える前から、魔女は口を開いて呪文を唱えるように言葉を放ってくる。
「楽しみにしていた私の百年を盗んだんだもの。猛毒が体に回って苦しんだとしても、それは自業自得よ。天使のように真っ白な、あなたの大切な子は魔女の呪いにかかったの」
魔女の呪い。本当にそうかもしれない。あの子は苦しんでいる。だからここに来たのだ。
あの子は、百年に一度咲くという魔女の花を盗んだ。望んだ姿になれるという幻の花。
「他の何かになれるわけなんかないのに」
憧れが彼女を蝕んだ。
「なれるわよ」
唇を噛み締めてうつむいた少年に向かって、魔女は言う。
「あなたが戻る頃には彼女は猫になっているわ」
顔をあげた少年の目には驚きが滲んでいた。パクパクと口から吐き出した言葉を代弁するなら「信じられなかった。いや、信じたくなかった」といったところだろうか。
「ここにもう一輪あるの」
魔女が怪しい笑みで差し出してきたものを少年は掴む。
飛び出していくその背中に、迷いはどこにもなかった。
* * * * * *
魔女はポツンと一人、不思議な店の中にいた。
「彼も猫になる道を選んだかしら、それとも彼女を人間に戻すのかしら」
くすりと静かに笑う魔女の足元に一匹の猫がすり寄ってくる。月のように銀色の毛並みをした青い目の猫。魔女はそっと抱き上げて、猫の額にキスをする。
「また百年、待ってくれる?」
そう声をおとした魔女をなぐさめるように、猫はニャーと、優しく鳴いた。(完)

Tales Recordとは
当サイトの「日常の中にほんの少しの非日常を」を基盤に作られた個人短編集です。「今日もこの世界のどこかで生きている」をキャッチコピーにしています。なさそうであり、ありそうでない。そんな狭間のお話たちの試し読みができます