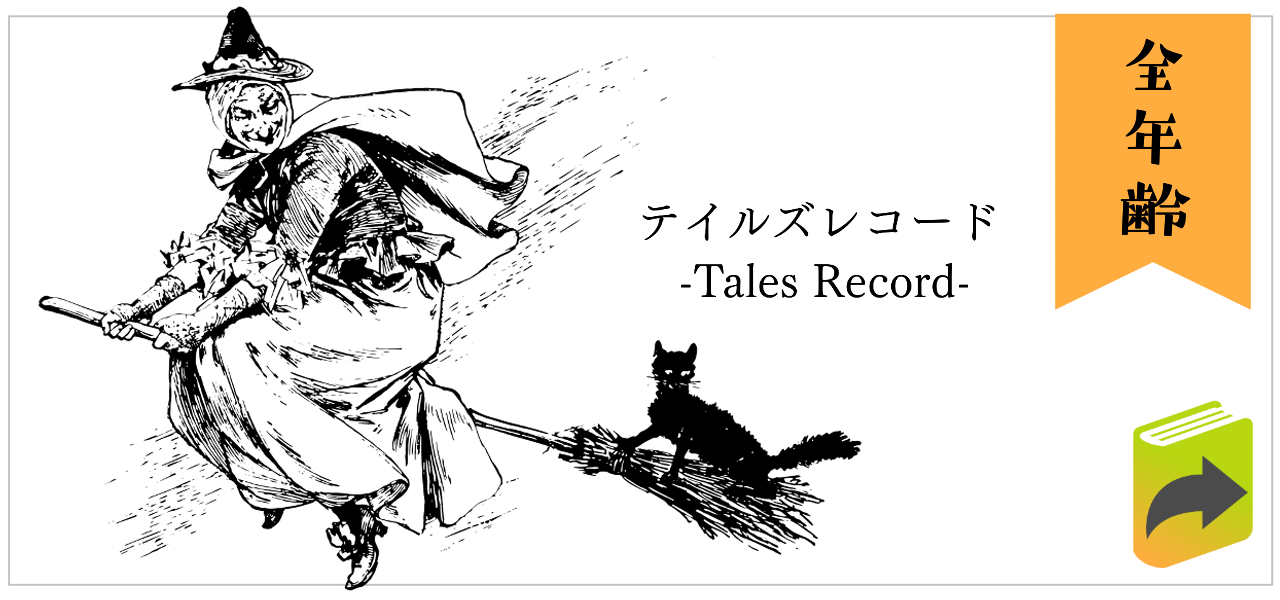喫茶店で冷めないコーヒーを(ありふれた魔女たちの日常より)
この作品は、2018年9月発行「ありふれた魔女たちの日常」に収録されました。
喫茶店で冷めないコーヒーを
永遠に冷めないコーヒーなんてこの世にはない。時間がたてば自然に湯気は消え、カップの中味を飲み干すころには最初の熱さなんて忘れている。そんなものだ。それが疑うことのない常識であり、人間の日常。
「こ、ここかな?」
地図に乗ってる場所と今の位置を確認する。
喫茶「マドモアゼル」
いかにも古めかしい外観だが、美味しそうなコーヒーの引き立つ匂いは外にまでその魅力を放っている。
「いらっしゃいませ」
カランカランと、どこか胸の落ち着く呼び鈴が店内に鳴り響き、カウンターにいた女性が落ち着いた声で入ってきたばかりの客を出迎えた。いや、正確には客ではない。
「あ、あの」
たどたどしい口調で、青年は店内に足を踏み入れる。再び、カランカランと心地いい音を響かせながらドアは閉まっていった。
「ああ、新しいバイトの子ね。そこに座って待っててくれる?」
沸いたお湯がフィルターに注がれていく。またふわっと鼻腔をくすぐるコーヒーの香りが店内に充満していった。
店内に客は三人。
一人は一番奥で新聞を広げながらコーヒーを飲んでいて、あとの二人は今、彼女が入れているであろうコーヒーを待っているのか、雑談をしながら過ごしている。静かな店内。何時間でも過ごせそうな落ち着いた雰囲気が、たぶん人気の秘訣なのだろう。
「コーヒーだって美味しいのよ」
そういって、先ほどまでカウンターにいたはずの女性が目の前で笑っている。
「はい、どうぞ」
「え?」
差し出されたカップに入った真っ黒の液体は、白い湯気をたてて美味しそうに揺れていた。
「まずは飲んで、面接はそれから」
ウインクなんて、生まれてこの方、一度もされたことがない。アルバイトの面接に来ただけなのに、コーヒーをすすめられるばかりか、女性に見つめられながら飲むことになろうとは想像もしていなかった。
「あ、あの」
「緊張して味がわからない?」
ニコニコとどこか楽しそうなのは気のせいではないだろう。
「どんな子が来るかなって思ってたんだけど、へぇ、キミかあ」
じろじろと上から下まで対面で見つめられるとたまらない。怖気づいたのか、少年はカップをテーブルに置いて席を立とうと体をすべらせた。
「待って」
「あ、あの」
この店に入ってから「あ、あの」の三文字しか発していない。もともと口が回る方ではない少年が、なぜアルバイトに接客業を選んだのかはわからないが、それはこの店主らしき女性のほうが明確な理由を持っていそうだった。
「私、マドモアゼルの店主のマドモアゼル」
「あ、はい」
「まあまあ、コーヒーをどうぞ」
「あ、あの」
「いいからいいから」
すっかり彼女のペースに魅せられて、話が前に進まない。
短い茶色の髪に、薄い化粧をした自称マドモアゼル。本名なのかどうか疑わしいが、少年は断り切れずに再度そのコーヒーに口をつけた。
「熱っ!?」
一度口をつけたコーヒー。数分の時間がたっているはずなのに、運んできたときと変わらない熱さに驚いた舌が火傷をしそうなほど熱い。
「これが、うちの名物。飲み終わるまで冷めないコーヒー」
自慢気にニヤリと笑うマドモアゼル。
その顔に見惚れたのか、少年は視線を誤魔化すようにコーヒーカップをテーブルに置く。
「あ、あの」
「キミいつからこれる?」
「あ、あの」
「じゃあ、明日からよろしくね」
気付けば握手をしているのだから意味がわからない。それになんだか自称店主の彼女はとても嬉しそうだった。ここで断るなんて無理な話。ふいに不安に襲われてくるが、脈絡についていけない思考回路が深く考えることを拒んでいるようだった。
「私と相性のいい人にしか見えない求人に反応してくれたのはキミが初めてなの。大丈夫、私たちきっとうまくやれるわ」
その自信はどこからくるのかわからない。それでも、全部彼女の言うとおりだった。
飲み終わるまで冷めないコーヒーを提供する店マドモアゼル。あの日から五十年。少年とマドモアゼルは今もあの店で二人仲良く働いているらしい。(完)

Tales Recordとは
当サイトの「日常の中にほんの少しの非日常を」を基盤に作られた個人短編集です。「今日もこの世界のどこかで生きている」をキャッチコピーにしています。なさそうであり、ありそうでない。そんな狭間のお話たちの試し読みができます