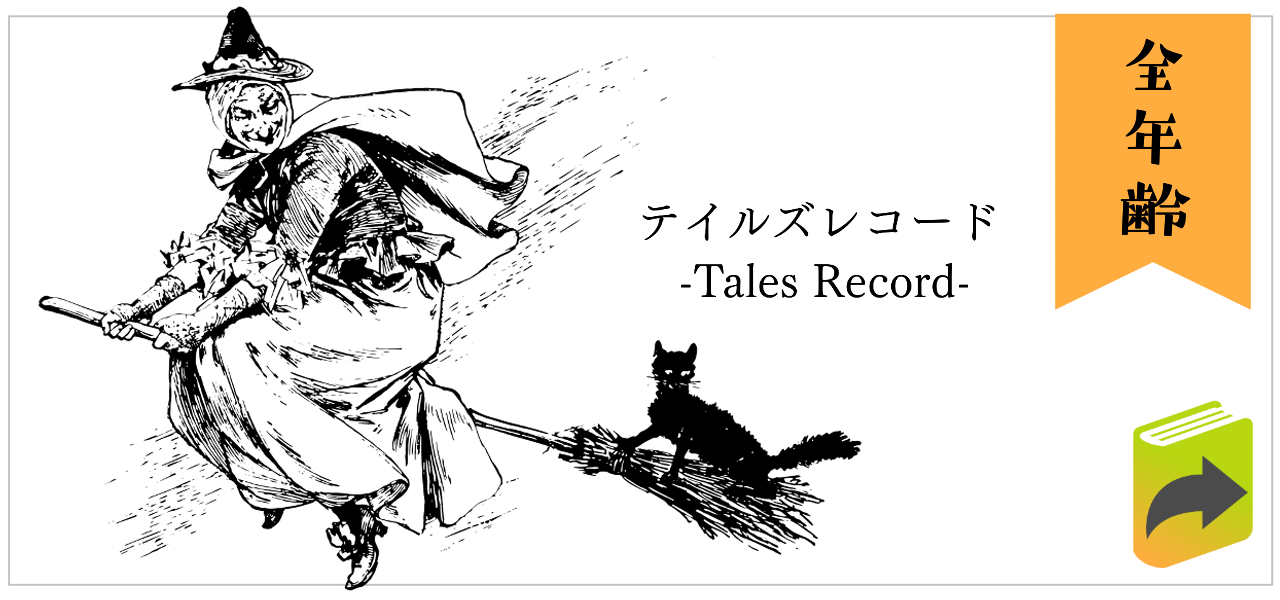煙突掃除夫の小さな宝石箱(うばわれた人魚たちの栄光より)
この作品は、2019年9月発行「うばわれた人魚たちの栄光」に収録されました。
煙突掃除夫の小さな宝石箱
その小さな宝石箱は古い暖炉の裏側に隠されていた。
特別見つけようと思って見つけたわけではない。それはただ偶然、煙突掃除をするために煤だらけになった少年の手に触れた。
「なんだこれ」
貧しい農村から金持ちの家に売られ、その金持ちの家も新しい煙突掃除夫を雇うことにしたとかで、お払い箱になったところを少年は今の主人に拾われた。初仕事だと言わんばかりに気合を入れた初日のことだった。
安直に主人の秘密に触れてはいけない。
それが意図的であろうとなかろうと、下層階級でしかない身分に待っているのは厳しい体罰だけ。
「俺は見てない」
少年は真っ黒な煤だらけの顔で宝石箱に呟くと、そっと元あった場所へとその箱を戻した。
* * * * *
子どもがやっと一人入れるほどの四角い筒は、屋根を貫いて空まで高く伸びている。下から上へ、上から下へ。指定された時間内に往復して仕事を終える頃には、見事なまでに全身真っ黒に染まっている。
「…………はぁ」
煙突から這い出て、屋根の上でくつろいでいると先ほどの記憶がよみがえってきた。
小さな宝石箱。最近誰かが触れた形跡はなく、忘れられたように暖炉の裏側に存在していた。誰かが隠したことさえ忘れてしまったように、それだけがポツリとそこにあった。
「何が入っているんだろう」
興味がわかないはずがない。想像よりも少し重くて、鍵もかかっていなかった。音が出ることを恐れて振るなんて馬鹿な真似はしなかったが、それでも想像は膨らんでいく。仮に宝石ひとつ入っていたとして、それが主人さえも忘れるほど大昔に隠されたものだったとしたら、持ち主は見つけた少年に変わるかもしれない。
「馬鹿馬鹿しい」
家のモノに手を出せばどうなるか。それを知らないほど子どもではない。
少年は黒い全身をいたわるように、屋根の上に寝転んだ。青い空に薄い雲が幾重にも覆っている。今夜は雨かもしれないなと、少年は湿気を孕んだ風に退屈そうな視線をそっとつぶった。
「そんなところで何をしているんだね」
からかうような老婆の声に、少年はパチッとつぶったばかりの瞳をあける。
半身を起こして声の出所を探ってみると、まさしく真下の階から老婆が悪戯な笑みを浮かべて手を振っていた。
「大奥様」
少年は慌てて体を起こすと、居住まいを正してぺこりと頭を下げる。この屋敷の主人は男性だが、その彼の母親にあたる老婆は、少年が来る前から屋敷にある最上階の角部屋で療養生活をしているらしい。
「堅苦しいのは嫌いさ。ちょっと降りといで」
「でも」
「口答えも嫌いさ。なあに、心配しなくともお前さんが怒られるようなことにはならないよ」
ひっひっひと肩を揺らして老婆は窓から部屋の中へと姿を消してしまった。
素直に追いかけるべきかどうか。迷っていても選択肢は一つしか存在しない。
「やあ、よく来たね」
全身黒ずくめの少年は、屋根から滑り込むようにして老婆の部屋へと足を運んでいた。
「お前さん、今日から雇われた煙突掃除の坊やだね」
「はい」
「アレ、はもう見つけたかい?」
「はい?」
しわだらけの顔にキラキラとした大きな瞳。若いころはそれなりに美人だっただろうが、今は年齢と共に失われたものが沢山あるように見えた。
「知らないとは言わせないよ。暖炉に隠された小さな宝石箱のことさ」
老婆の言葉に少年は思わず顔をこわばらせる。先ほど屋根の上で思いをはせていた小さな箱の存在を見透かされたようで、休息に喉が渇いていく気配が少年を襲う。
そんな少年のわずかな変化に気づいたのか、老婆はわかりやすいほどにっこりと笑みを深めてこう言った。
「あの箱をこの屋敷の住民の誰一人に知られることなく、わしのところへ持ってきなさい」
それはまるで呪文のように、少年の耳にこびりついた。
だからと言って、少年がすぐに煙突に隠された小さな箱を老婆に持っていったかと言えばそうではない。何が罠で、何が真実なのか下層階級に位置付けられた者にとって、あるべき場所からものを移動させるのは相当の覚悟がなければならない。そして幾日かが過ぎ、何度目かの煙突掃除のあと、少年は寝込んでいるらしいと小耳にはさんだ老婆の部屋に煤だらけの格好で訪れた。
「慎重な坊やだね。まあいい、わしが死んだあとあの箱の中にあるものは坊やの好きにしたらいい」
ゴホゴホと、老婆は先行きの思わしくない咳をこぼしながらそう言った。
ぼんやりと天井を見つめ、苦しそうな息を吐き出している。
「大奥様」
「やめとくれ、そういう風に呼ぶのは」
ベッドに横たわった体で老婆は自嘲の笑みを少年に向ける。
「わしは、大奥様ではない。大旦那様に捕えられた哀れな人魚の成れの果てさ」
「人魚?」
「そうさ。こんな海も見えない国じゃ、信じられないだろうが、人魚は深海に住み、人間を誘惑する海の化身。ちょっと人間の世界で遊んで帰るだけの予定が、まんまとあの悪党に騙されて気づけばこの有様さ。暖炉のアレは随分前に失くしたとばかり思っていたが、大旦那様がわしから奪って隠したらしい。誰もわしにその箱を持ってくることはできなかったがね」
「中には一体何が」
「わしが人魚である証だよ」
老婆は懐かしむように天井に向かって骨と皮だけになった細い腕を伸ばしている。少年は弾かれたように窓から屋根に飛び出し、煙突を滑り降りるように伝って、例の小箱の場所までたどり着くと大急ぎで老婆の元まで戻ってきた。はあはあと息がきれるのも無理はない。
少年は寝具にもぐる老婆の場所まで黒い姿で近づくと、手にした小箱の蓋をそっとあけた。
* * * * *
煙突掃除は今日も無事に終わりを告げる。
黒い煤だらけの身体でいつものように屋根の上でくつろいでいると、ポツリと小さな雫が少年の頬にそっと流れた。
「雨だ」
呟いた声にこたえるように、降り始めた空の涙は次々と大粒になって少年の身体へと降り注ぐ。いつかみた灰色の空。人魚だと正体を明かす前の老婆と出逢った日も灰色の雲が上空に立ち込めていた。
「ああ、約束はちゃんと守るよ」
少年は誰にでもなく雨の中で一人呟く。
右手には煤を掃う箒を持っていたが、それをおもむろに屋根に置くとポケットの中から取り出した小さな破片を空に掲げた。雨がまた、ポツリと少年の頬を撫でる。
老婆が残していったものは実に小さなものだった。
宝石でも、金品に変わるような代物でもない。ましてや少年を下層階級から引き揚げてくれる価値あるものでもない。それでも少年は、それが暖炉に隠すだけの価値があることを知っていた。
「いつか海へ」
虹色に光る薄い鱗だけが、少年の伸ばした指の先で静かな雨の中を泳いでいた。(完)

Tales Recordとは
当サイトの「日常の中にほんの少しの非日常を」を基盤に作られた個人短編集です。「今日もこの世界のどこかで生きている」をキャッチコピーにしています。なさそうであり、ありそうでない。そんな狭間のお話たちの試し読みができます