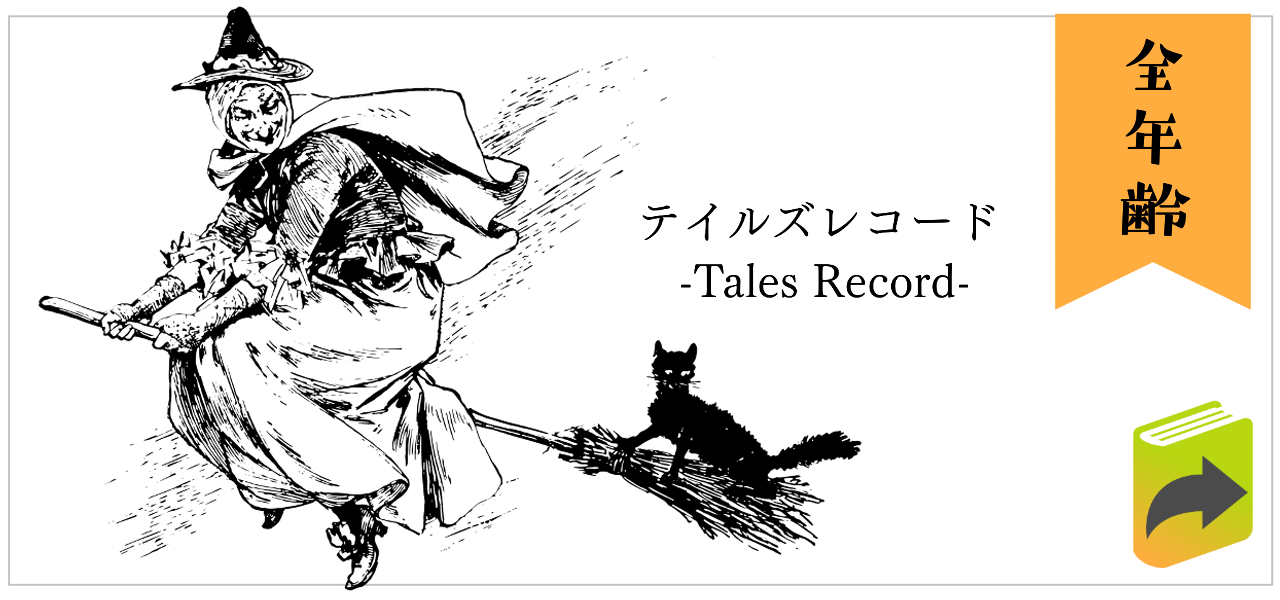北の王子と水中の踊り子(うばわれた人魚たちの栄光より)
この作品は、2019年9月発行「うばわれた人魚たちの栄光」に収録されました。
北の王子と水中の踊り子
海に溶けるほど青い自慢の長髪を揺らして、彼女はクルクルと踊っていた。水中都市を旅する曲芸団の踊り子レリーニャは全人魚の憧れの美少女。洗練された砂のようにきめ細やかな白い肌と星のように煌く金色の瞳。流れるしなやかな尾ひれは動くたびに色を変え、彼女がひとたび舞いを踊ると、その場の水はすべて彼女を祝福したという。
容姿もさることながら性格も控えめで大人しく、媚びない低姿勢が老若男女問わずに歓迎される有名な少女。
その彼女がこうして城に招かれて、自慢の容姿をふるうのも納得がいく光景。
しかし、たった一人だけつまらなさそうに無表情のまま彼女をみている男がいた。
「もうよい」
片手をあげて男は少女の舞いの中断を命じる。
くるりと身体を回しかけていたレリーニャは突然曲が止まったことに疑問を感じて、次いで、片手をあげたまま無表情に見つめてくる男を見つけて、慌てて頭を下げた。
「国王様、いかがなされましたでしょうか」
レリーニャの代わりに、男の隣に立っていた中年の男が言葉をかける。きっとその場にいた誰もがその質問に耳を傾けていた。なぜなら玉座に腰かけ、この海域一帯を取り仕切る人物の言葉は他の何よりも重たい。彼が首をはねろというのなら、たとえレリーニャが全国民の憧れの存在であったとしても呆気なくその命は終焉を迎えるだろう。
「余は疲れた。祭りはもう終わりだ」
黄金の尾ひれが力強い波立を生む。
若くして王になったミザは、前王の無能さから荒れ放題だった周辺海域をまとめあげた手腕ぶりが高評価されていたが、同時に若さゆえの気まぐれも併せ持っていることで有名だった。頭を下げたまま微動だにしないレリーニャを見てどう思ったか定かではないが、ミザ王は自身の持つ黄金の尾ひれを再び動かして、その場の水流を城の外へと追い出した。
「国王様、よいのですか?」
「なにがだ」
先ほどミザ王に話しかけた男は、その鋭い視線に射抜かれて言葉を濁す。
すっかり客人のいなくなった城内で二人きり。それでも心休まることのない張り詰めた空気に、男の方が頭を下げて国王に折れる形でおさまった。
一方、きちんとした理由もなく突然城を追い出されたレリーニャは最初呆気にとられていたものの、今はひとり憤慨していた。
「信じられない」
夜も更けた海は暗く、予想もしていなかったまさかの仕打ちが心にしみる。ここで泣けるほど可愛げがあれば外見に似た性格なのかもしれないが、レリーニャは涙など何にもならないと言わんばかりに大きく尾ひれを動かして、城の裏手にある珊瑚の庭に逃げ込むと盛大な声で悪態をついた。
「なんなのなんなのなんなの!あの男、頭おかしいんじゃないの。王様がどれだけ偉いか知らないけど、人の踊りを最後まで見もせずに追い出すなんて最低よ。あんなのが国王でこの海域の民は可哀そう。随分と慕われている王様みたいだったから、私もすごく期待していたのに、とんだでまかせよ。みんな騙されているに違いないわ」
はぁはぁと、レリーニャは肩で息をするように唇を噛み締める。
こんな屈辱は初めてだと、握りしめた両手のこぶしの行き場さえ思案してしまうほどだった。
「なんだ元気じゃないか」
「だれっ」
驚いたのも無理はない。
表では品行方正で通っていることはレリーニャ自身も知っている。レリーニャに憧れの眼差しを向ける一般市民は、王宮からレリーニャが追い出されたことを信じはしないだろうが、仮に追い出された場合「か弱いレリーニャ」が罵詈雑言を口にするはずはないと口をそろえて言うだろう。
しかし、現実は違う。
必死な言い訳を頭に思い浮かべていたレリーニャは、暗がりの中から現れた姿に息を呑んで固まった。
「ミザ王、なんっ」
「声がでかい」
腰を引き寄せられて、抑えられた唇がミザ王の手の大きさを物語る。衛兵らしき海流が疑問符を浮かべたまますぐ脇を通り抜けていくような気がしたが、レリーニャにとってはそれどころではない。
ミザ王が口を押えてくれていなかったら、今頃きっと心臓が飛び出していたに違いない。
先ほどの悪態を聞かれたかもしれないと思って言い訳を探してたが、当の本人相手では言い逃れすら難しい事実。ましてや悪名高い若い王のこと。レリーニャの言葉を笑って受け流してくれる器量の持ち主とは思えない。
「随分と噂と違うな」
耳元で囁くような低音がすぐ近くから聞こえてくる。
「もっももも申し訳ございません」
そう大声で謝罪したいところだが、ミザ王本人の手によって口を塞がれたままのレリーニャの口からはプクプクと可愛い泡しか出てこなかった。バタバタと色を変える尾ひれを必死に動かしてみても、金色の尾ひれを持つ王の前ではふぐのひれくらいの効力しかないのだろう。結果として、逃げることの出来ないままレリーニャはミザ王と密接したまま、いつ死が訪れるのかと混乱していた。
「まあ、そう緊張するな」
「っ」
至近距離で覗き込んでくる視線が熱い。ミザ王が治める国の女性たちがみな噂していたが、たしかに落ち着いてよく観察してみると、その端整な顔立ちに心奪われない人魚などいないと断言できるようだった。真珠のようになめらかな白髪、金色の尾ひれと同じ黄金の瞳。均整の取れた上半身は女性が一人必死に暴れようと、赤子のようにあやしてしまう。
「さっきは悪かった」
思いがけない王の謝罪に、レリーニャの抵抗がパタリと静かになった。
「なぜ、私は追い出されたのでしょう?」
「つまらなさそうに踊っていたからだ」
「え?」
「知らないだろうが、劇団に入る前に酒場で踊っていたお前を知っている。形式にとらわれず自由に踊る姿に魅了され、それでいいのだと勇気をもらった。周囲の声を気にして仮面をつけなくても、ありのままが一番好きだ」
レリーニャの金色の瞳が同じく金色に輝くミザの目を見上げる。
暗い海の底でゆらゆらと煌めく二つの星は、互いの色を確認し合うように不安定に揺れていた。
「余の妃にならんか?」
「いやです」
反射的に拒否を口にしてから、レリーニャはハッと気づいたように口をつぐんだ。
どうもこの王様の前だと調子が狂う。いつもは聞き分けの良い大人しい少女を演じられるのに、ひとつの失態から繋がる一連の流れのせいで、つけていた仮面ごと波に流されてしまったようだった。
「あの、これは、その」
言葉を探して狼狽えるレリーニャの尾ひれがパタパタと揺れる。そしてなぜか、王は嬉しそうにレリーニャの腰を抱いたままでいた。
「それは残念。だが―――」
「あっ」
さらに至近距離に迫る金色の瞳は、にやりと悪戯な笑みを浮かべてレリーニャの本性を喜んでいるに違いない。
「―――余は欲しいものを逃したことがない」
パクパクと言葉にならない泡を吐き出すレリーニャの唇は、次の瞬間、深い愛に包まれる。
後に北の海底を治める王の傍らに、虹色に光る尾ひれが波を作るのは有名な話。けれど、今はまだ珊瑚の庭で乙女の唇を奪った王の左頬が殴られる出会いの物語。(完)

Tales Recordとは
当サイトの「日常の中にほんの少しの非日常を」を基盤に作られた個人短編集です。「今日もこの世界のどこかで生きている」をキャッチコピーにしています。なさそうであり、ありそうでない。そんな狭間のお話たちの試し読みができます