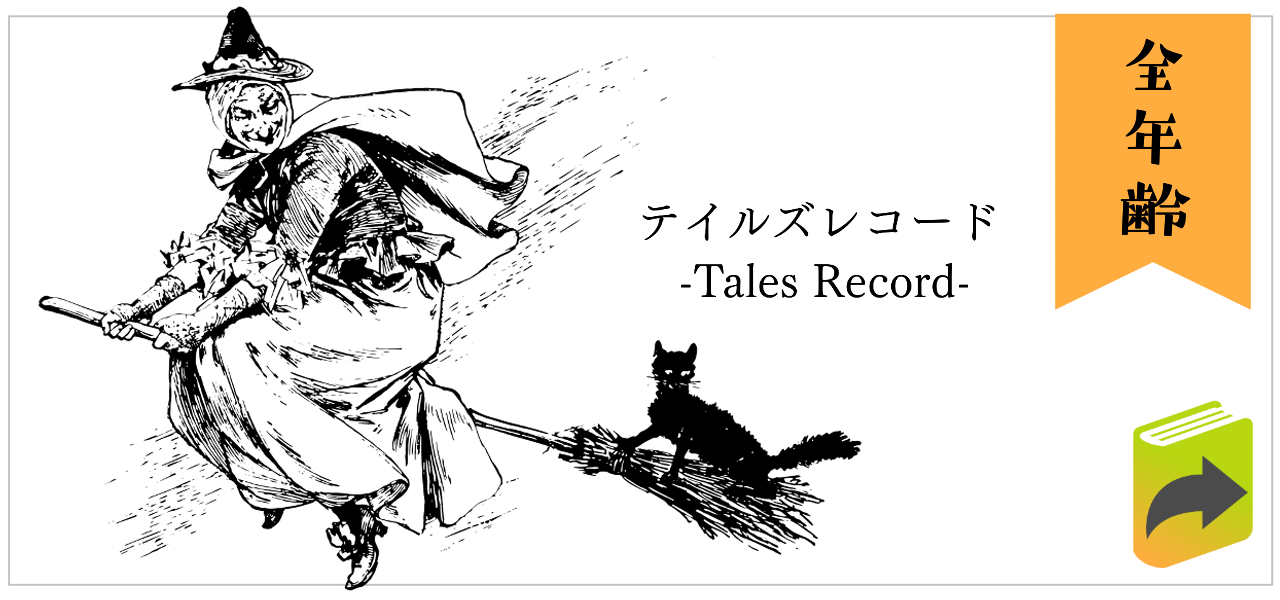王女の涙(かたられる宝石たちの秘密より)
この作品は、2020年5月発行「かたられる宝石たちの秘密」に収録されました。
王女の涙
歴史書に残る文面の欠片でも、当時を生きる人々にとっては一生を左右する濃密な時間だったりする。つまり「跡継ぎのいなかったシルビア国は盗賊と呼ばれた男を王に迎え入れ、美しい王女と結婚し、国は最大の発展を遂げた」などという馬鹿げた一文があったとしても、そこにまつわる物語は決して一文なんかでは表現しきれない時間の経過を伴っている。
これは、魔法が生きる砂漠の国。シルビアで起こった奇跡のような実話。
* * * * *
行商人たちがテントを張って軒先に果物やパン、香辛料を並べる朝。不思議な形をした壷、色彩豊かな絨毯、時々店主に紛れてカルカルという生物が鎮座しているが、シルビア国で当然のように存在する生物を今更不思議がる人もいない。
新鮮な乳を出し、温厚で人懐こい、くわえて荷物運びはもちろん人を乗せて何時間も砂漠を横断しても疲弊しない屈強さを持っていれば自然と家畜として重宝される。シルビア国に住む人々はカルカルの頭数でその家の位を知る文化が残る程度には、馴染み深い存在と言ってもいいだろう。
「今日も平和そうね」
「はい、シェリル様」
緑の少ない砂漠に置いて、シルビア国の王女シェリルの髪は至宝と呼ばれる美しさを誇っていた。腰まで伸びた艶やかなエメラルドグリーン。真っ白な肌に、大きな瞳。緑に愛されたその瞳で見つめられると、誰もが一目で恋に落ちると囁かれている。
一方で、それは魔女の仕業だと。王をたぶらかし、王妃を殺し、シルビア国を乗っ取る算段を企てた魔法使いが美しい王女のフリをしているのだという噂もある。シェリルを小さなころから見守って来た王宮の人間は何を言っているのかと、ため息交じりにあしらうが、広大な国では一定の確率でシェリルは魔法使いだと支持している声がある。
「ここはもういいわ、下がって」
静かに召使の退却を命じたシェリルの手に、数人の召使たちは頭を下げて部屋を出ていく。
朝の身支度。
頭に乗せられた王女の証も、腕輪も首輪も耳飾りも何もかもが煌びやかな緑色の宝石で装飾されている。
「あー、もう重たいっ」
シェリルは誰もいなくなったのを見計らって、頭の上に載っていた装飾品を取り外す。手のひらほどの大きさを誇る緑の石を中央に金細工で輪になった装飾品は、弧を描いて目の前のクッションに投げられた。
「窮屈だわ、息が詰まりそう」
どうせ今日も見合いだろう。年頃の一人娘を持つ国王としては、一日も早く世継ぎとなる王を目にしたいと望んでいる。病弱な王妃はシェリルの幼いときに亡くなり、王宮には父と娘の二人きり。先行きの不安はひとつでも多く失くしておきたいという王の心情はわからなくもないが、まだ十八。規律やしきたりよりは自由を謳歌したい年頃。
「さあ、魔法の石。今日も出番よ、私の見合い相手の顔を映して」
指を絡ませて伸びをしたシェリルは先ほど頭から取り落としたばかりの装飾品に向かって呼びかける。本来の役割はどうか知らないが、外の世界から隔離されたシェリルにとってその意思が見せる世界がだけが外界を知る唯一だった。
「あら。ミューミヒ大臣の三男坊。ジーアスじゃない」
緑の石の中に歪んで映るのは、何度か顔を合わせた相手。
階級を重んじ、金で物事を決める嫌味な男。
「次は、トッティラ王国?」
今度は生理的に無理な相手すぎて何も言葉が浮かんでこない。
日々やってくるのは金にものを言わせた調度品と歯の浮くような台詞ばかり。シルビア国の所持する土地と資源を考慮すれば、周辺諸国からは是が非でもこの好機をものにしたいのだろう。
「残念、今日も退屈な日になりそうだわ」
はぁっと深い息を吐いてシェリルはクッションの上に横たわる。
どれほど美しいと称賛される容姿をもっていても駕籠の中の鳥と同じ。本当の美しさとは何か。答えられるものを持っていない人が吐き出すお世辞など、出来ることならこれ以上聞きたくもない。
「じゃあ、そろそろ逃げますか」
まだ何かを映そうとしていたが、どうせ大差ない男の顔を映すだけだろう。
シェリルは脱ぎ捨てていた髪飾りを手に取って立ち上がる。
扉の方に衛兵は控えているかもしれないが、庭を一面見渡せる吹きさらしの窓にその姿は見えない。広い迷路のような王宮でも小さなころから遊び場として駆けまわって来たシェリルにとって、面倒な見合いから逃げる場所なんていくらでもある。長い髪をひとつに束ねたシェリルは、窓枠をよじ登って庭に出ると、木々の合間を縫うようにして人知れず自室から逃げ出すことに成功した。
「久しぶりにマーラのところに行ってみようかしら」
東の建物には王家の人間以外立ち入り禁止になっている区画がある。そこには千年を生きる魔法使いがいるとされ、現に年齢不詳の老婆が王国の未来を占うことがあった。
「最近、パパがよく足を運んでいるみたいだから鉢合わせしないようにしなきゃ」
連日続くお見合いを抜け出すのはこれで二回目。普段、王として何をしているのかは知らないが、召使たちの話では「国王はマーラ様のところに頻繁に足を運ばれている」のだから気を引き締めておくのに越したことはないだろう。
言っている傍から、マーラの在中する部屋の前から王の声が聞こえてきた。
シェリルはとっさに身を隠して、その声が通り過ぎるまで息をひそめることにした。
「マーラ様、それは本当ですか。いや、本当なのでしょうが、それはあまりにも」
「ほっほっほ。王よ、運命の歯車は人の子にはどうしようも出来んよ」
「しかし、娘の結婚相手はこの国の次期国王なのですぞ」
「それがどうした。そなたとて、身分、階級関係なく王妃を娶っただろうて」
「王妃は由緒ある家系の娘だった」
「結果論じゃろう。まあ、魔法で見る落ちぶれた婆の言うことじゃ。王の思うように見合いでもなんでも続けておれば、予言される未来も少しは変化を見せるというもの」
「わしはそれに期待する」
「ほっほっほ。楽しみじゃの」
焦燥を隠しもしない父親の足音が飛び出すように去っていく。見つからなかったのは運が良かったのかもしれないが、先ほどの話の流れでは、今後ますます見合いの回数を増やされるかもしれないという事実にゾッと悪寒が駆け抜けた気がした。
「シェリル」
「はっはい」
突然、自分の名前を呼ばれて息が止まるほど驚いた。
どうして隠れていたことがバレたのか。千年を生きる魔法使いの前ではその疑問すら何の役にも立たないだろう。
「久しぶりじゃな。どれ、近う寄れ。おお。これはまた一段と美しくなったもんじゃ」
相変わらず何をかき混ぜているのか、小さな鍋を火にくべながらマーラは黒い頭巾をかぶって部屋の中央に座っていた。シェリルは当然のように身を隠していた場所から這い出て、マーラの前に座り込む。
「マーラ様、さっきの話」
「ああ、王も頑固さは生まれつきゆえ、気にするでない」
「でも私、もうお見合いは嫌なの」
「それで抜け出してきたのか?」
本当にどこまでもお見通しなところが恐ろしい。深いしわが刻まれたマーラの顔の表情を読むことは出来ないが、ちらりと覗いた緑の瞳は、未来の自分を眺めているようでどことなく気味悪い。
そんなシェリルの居心地の悪さを察したのか、マーラは服のたもとからごそごそと小さな瓶を取り出す。
「おぬしは王妃によく似ておる。そうだ、これを持っていけ」
「これってケガのときに塗る薬じゃない」
「役に立つ」
「もしかして私、ケガするの!?」
これは魔女の報復だろうか。考えていたことが読まれた結果の証明といわんばかりの品物に、シェリルは青ざめた顔でその瓶を受け取っていた。
「ほっほっほ。運命とは良くも悪くも来るべき時に来るものよ」
引きつった笑みしか返せなかったのはいうまでもない。
早々にマーラの部屋から退散して、シェリルはどうしたものかと廊下を一人歩いていた。東の塔に人はほとんどいない。時々見回りに歩く兵がいるだけで、彼らも王と王女以外の人間が訪れることがないと高をくくっているのか、少し身を潜めていれば問題はない。
いつもであればそうだった。
けれど、今日はどうも様子が違うらしい。
「いたか」
「いや、確かにこっちの方に逃げたはずだ」
「手負いの獣だ、そう遠くには行けない」
「まさか、マーラ様を狙って」
「そうでなくても王女誘拐の罪だ、急げ」
バタバタと駆けていく衛兵たちの気迫が尋常じゃない。しかも身に覚えのない会話を残している。
王女誘拐?
シェリルは自分で自室を抜け出しただけだというのに、いつの間にそんな話に飛躍したのだろうか。考えても疑問だけが浮かんでは消えていく。大事になってしまった事態を鎮めるには素直に謝ってしまう方が得策だろう。
「はぁ、仕方がないわね。このままパパのところへ」
そう言って玉座までの近道を行こうと体の向きを変えたシェリルの息が止まる。一体誰が、そこに人がいることを予期しただろう。
手負いの獣。
たしかに、衛兵たちはそう口にしていたが、金色に光る瞳孔、牙を剥きだした荒い息は、今にも人を襲うためのうなり声をあげている。
「ヒッ!?」
反射的に込み上げてきた悲鳴ごと壁に抱き寄せられる。濃厚な血の匂いがシェリルを包むが、それ以上に凍てつくほど獰猛な金色の瞳の怒りに意識が奪われてしまいそうだった。
「殺されたくなければ静かにしろ」
はぁはぁと苦しそうな声に男だとわかる。
無言で震える顔で、了承の頷きを返すと男は少し力を抜いたように手を離した。
ホッと息が返ってくる。酸素のありがたみを深く吐き出したところで、シェリルは目の前の男を観察し始める。年は近く、粗暴だが綺麗な発音をしている。服装を見る限り貧しい身分の者であることは明らかだが、それ以上に人目を惹く美しい瞳を持っている。こんな場所になぜ。その疑問は青年の口から語られることはないのかもしれない。
「あなた、誰なの?」
わかっていても聞いてしまうのは仕方がない。
「ケガ、してるの?」
思わず伸ばした手を勢いよく弾かれる。「オレに触れるな」と短い言葉と共に睨まれた瞳は、やはり何度見ても綺麗以外の感想が浮かんでこない。人によっては怖いと思うのかもしれない。それでもシェリルにとって彼の持つ魅力は、放置できる価値ではなかった。
「こっちに来て」
「いいからオレに」
「こんな場所で死にたくないでしょ」
弾かれた指先が痺れている。本当は怖くて震えていた。それでも気付かないふりをして見ず知らずの男の手を取った自分の行動に説明はいらない気がした。助けたい。そう思うよりも前に動いてしまった体は、素直に従うフリを見せた男の手を引いて自分の部屋へと繋がる隠し通路を歩いている。
「お前、シェリル王女か」
「人の名前を言い当てる前に自分の名前を言うべきね」
「王族は嫌いだ」
「安心して、私も嫌いだから」
他愛ない押し問答を繰り返しながらシェリルは手負いの獣を連れて歩く。石を削っただけの通路はどこまでも暗く狭いが、空気の流れは安定して漂い、不思議と守られているような温かさを感じられる。
「さっきから光ってるその宝石たちはなんだ」
「え、光ってる?」
足を止めたシェリルは言われて初めて、頭に乗せた髪飾りだけでなく全身につけた緑の石が発光していることに気が付いた。確かに光っている。ただ、なんだと聞かれて答えられるだけの情報は持っていない。
「気づいてなかったのか、この通路は魔力に満ちている。その宝石がなければ骨になる未来が待っているだろうな」
自分よりも情報に通じる一般人に興味がわかないといえば、それも嘘になる。
ただ、口の悪さだけはお世辞にも良いとは言えなかった。
「王女の証を持っている人間が王女以外のわけがないだろ。オレを祭壇へ連れていけ」
「どうして一般人が王女に対して偉そうなのよ」
「オレには関係ない、今ここで噛み殺されたくなければ祭壇に案内しろ」
「祭壇?」
「その宝石を持つ者だけが入ることの許される、この王宮の地下神殿だ」
噛み殺すだけの余裕があるとは到底思えない貧血の獣に、シェリルの恐怖が薄れていく。仮にも同じ年頃の男女。今まで身近にいなかった存在に興味は募る一方だった。
「そこには何があるの?」
光を放つ緑の宝石並みに輝くシェリルの瞳が金色の瞳を覗き込む。
その勢いに押されたのか、一瞬、ぐっと唇を噛み締めてのけぞった男は、数秒思案したのち「魔人の笛」と小さく答えを吐き出した。
「それって、もしかしてこのくらいの大きさで、八つ穴が開いていて、緑の宝石がついた笛のこと?」
シェリルは思い当たるふしがあるのか、身振り手振りで大きさを表現する。両手に乗るくらいの小さな涙型の笛は、平たい壷のようになめらかな曲線を描いて、中央に息を吹き込むための突起がついている。豆粒ほどの小さな緑色の宝石が一粒だけはめ込まれた真っ白な笛。特徴は男の探しているものと完全に一致したらしい。
無言で一度だけ首を縦に振ったその瞳には、獲物を目の前にした獣の光が宿っていた。
「それなら私の部屋にあるわよ」
「は?」
「あはは、小さいころに持ち出して遊び道具にしていたんだけど、飽きたから部屋のどこかにしまってあるはず」
「あれはこの砂漠にすむ盗賊たちの憧れだぞ!?」
「あら、そうなの?」
「それを遊び道具に」
虚をつかれたように唖然とした男の声が脱力したのか、ずるずると通路に腰をおろしていく。
「王女が魔女って噂は本当だったのか、いや、これも計算の内か」
いったい何のためにケガまでして俺は王宮に忍び込んだのかと、自暴自棄にもとれる自嘲の声が聞こえてくるが、それこそシェリルにとってはどうでもいい話。
「笛、私の部屋に取りに行く?」
申し訳なさと同情をにじませたシェリルの誘いを男はまた、差し出された腕をはじくことで不服を現した。
「これだから王族は嫌いなんだ」
悲しみに打ちひしがれた手負いの獣をシェリルが自室に招くまであと一時間。マーラからもらった傷薬で男の傷が完治するまであと三日。そこから先の未来は歴史書に記された通り、美しい王女と盗賊は結婚し、国は繁栄の喜びを一文に刻んだ。
(完)

Tales Recordとは
当サイトの「日常の中にほんの少しの非日常を」を基盤に作られた個人短編集です。「今日もこの世界のどこかで生きている」をキャッチコピーにしています。なさそうであり、ありそうでない。そんな狭間のお話たちの試し読みができます