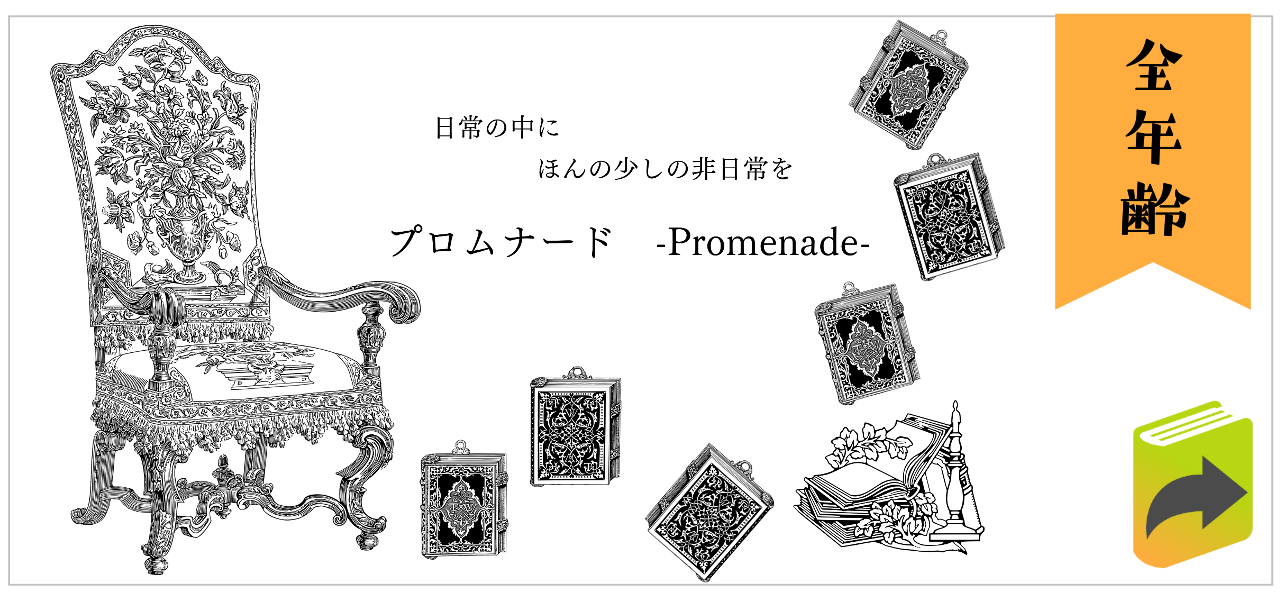読切「憧憬の色を掴むときには」
憧憬の色を掴むときには
読み:じょうけいのいろをつかむときには
公開日:2022/09/某日
ジャンル:SFファンタジー
文字数:約6200字
読了時間:約8分
タグ:恋愛/両片思い/夢/SF/巨大なイキモノ
本編「憧憬の色を掴むときには」
国境と名のつく境界線が、意味を成さなくなって百年。同じ思想を持つものだけが集まり、暮らすようになったのと等しい年月。こういう未来に至ったのは、生き残った先人たちの最期の本能だったのだろう。人類が滅亡しないための進化ともいえる。聞こえはいいが、結果的に、人間は自らを狭い檻の中に幽閉した。
最先端技術を総動員して作られたのは、自走型要塞都市Self propelling Fortress City。通称『SFC』。それは、昆虫や甲殻類、節足動物等を模して作られた都市を意味する。模して、というのは語弊がある。事実、突然変異で巨大化した彼らの死骸を利用した都市だと、今では周知されている。なぜなら、頑丈なその抜け殻も百年という年月には抗えず、次なる住処を求めて自走し続けているからだ。
死骸はそう多くない。
数を増やしすぎた人間を嘲笑うつもりで、天上人は恐竜以上の巨大生物を造り出したのだろう。天罰、終焉、新天地への誘い。歴史書が記す言葉は著者によって異なる。いずれにせよ、神々の遊びは突如として始まり、呆気なく人間は減り、自然は知らない未来へと舵を切った。
進化の早い彼らは、うまく適応しながら今の世界で生き続けている。だからこそ、人間は、未知なる巨大生物の寄生虫として暮らし、生き永らえているといっても過言ではない。
殲滅してきた数多の種類が辿った歴史と同じように。
現在、この地上に、人間の住む死骸『SFC』数百体が闊歩しているとはいえ、未来が明るいのは何体になるのだろう。聡弥(そうや)が暮らすのもまた、そのうちのひとつ『サソリ』と名付けられたSFCだった。サソリは縦に長く、大きな爪と尻尾を特徴とする。安易に武器だと告げるそれらは、外界の脅威に対し、槍として機能する。逆に、身を守る盾といえば、その身体。都市を内包するサソリの身体は全体的に乳白色、半透明で、頑丈な殻で構成されていた。
当然、地上を見下ろす空の様子をサソリ内に届けてはくれない。
利点はひとつ。空気が正常を維持している。寒暖差もない。雷雨に怯え、猛暑に焼かれることもない。ただ、ぼんやりと、好天と悪天を知らせるだけ。昼と夜を教えたとしても、それは日時を図る参考として、活用される程度に過ぎない。
ぼやけて見える暗幕の下。
外はもう、人間を受け入れない。
都市は、今夜も静かに就寝を共にしている。
一部の区画は眠らないが、それでも大半は百年前から変わらず、夜は静かに、家の中で過ごすものらしい。ここにいる、ひとりの青年を除いて。
サソリ内部にある丘に寝そべり、空を見上げる聡弥の瞳に映るのは小さな楕円。滲み、歪むそれが、今夜はやけに明るく見える。サソリから見える星はひとつだけ。人は太古からそれを月と呼んだ。
柔らかな月光は静寂と相まって、言葉にできない感傷を連れてくる。
手を伸ばせば届きそうな。けれど、人類は二度と月に足を下ろすことはない。
「聡弥(そうや)」
可愛い声で名前を呼ばれて、喜ぶどころか盛大な息を吐いた聡弥は、身体を起こして立ち上がる。
街灯の向こう側から駆け寄ってきた姿は、褐色肌に白銀の髪。水色の双眼。四季もなく、代わり映えのない風景のなかに溶け込んだ、見慣れた人物。
「利江娜(りえな)………ったく、こんな時間に、外に出るなよ。てか、こんな場所までついてくんな」
「冷たいなぁ、もう。愛しの彼女にする態度じゃないぞ?」
「そもそも付き合ってないし」
「そうだっけ?」
笑いながら隣に並ぶ気配もいつもと同じ。
同じ学校、同じクラス。くじ引きなどという古典的な組み合わせで、隣の席になったのが運の尽き。それから十五年の腐れ縁。二十三歳にもなれば、偶然でも必然でも「つるむ」なんていう感覚はない。
世間の目も、そうは見てくれない。
聡弥は首の後ろに手を当てて、どうすれば利江娜が立ち去ってくれるかを考えていた。
「毎回、毎回、飽きもしねぇで、俺にかまって楽しいか?」
「好きな人の傍にいるのは楽しいよ?」
「好きな人、ねぇ」
「うん。好きな人」
「お前さぁ、他に好きなやついねぇの?」
「聡弥以外に?」
「そう。俺以外に」
お決まりの文句。一緒に見上げる空には朧気な月がぽつりと浮かんで、ひとりは寂しいと告げてくる。
寒くなるはずのない気温が、人肌を求めて疼きだす。
だからイヤなのだ。厄介な感情を持ちたくないと、聡夜はまたため息を吐く。
「そんなに、ため息ばっかり吐いてると、幸せが逃げちゃうよ?」
「誰のせいだよ」
「え、あたしのせい?」
「他にいんのかよ」
「じゃあ、そのぶん補充してあげる」
「いらね」
これみよがしに抱きついてくる利江娜を聡夜は引き剥がす。男と女。力関係は一目瞭然なのに、利江娜は一向に離れていかない。
無意識に傷つけないよう配慮している力加減に嫌気がさして、聡夜は利江娜との攻防を諦めた。
「ねぇ、聡夜。大丈夫だよ。また、次があるよ」
「………なんで知ってんだよ」
「おばさんに聞いた」
「………………はあ」
口止めの意味は、歴史の渦に溶けて消えた。いや、この場合は仲が良すぎる母親と元クラスメイトの関係性が、聡夜に、そう思わせたのだろう。
サソリに住む人々の夢の象徴。憧れの司令塔。サソリの頭部に位置し、堅固な要塞都市のどこからでも視界に入る赤黒い巨塔。
腹部にある小高い丘の真正面。そこには、エリートと呼ばれるこの世の富、名声、栄誉が集結している。塔で働ければ生涯安泰。誰もが羨む豪華な生活が手に入る。塔に入るには実技試験と筆記試験、面接の三段階があり、今回、聡夜はその筆記試験に落ちた。
正直、五回目ともなれば受け止め方も慣れてくる。合否を知らせるメッセージの感覚で、開く前から結果がわかるほどには、見慣れた文面だった。
「諦めなかったら願いは叶うよ」
「五回も落ちてりゃ才能無さすぎだろ」
「でも、聡夜は飛びたいんでしょ?」
見上げてくる至近距離からの質問に、聡夜はすぐに答えられなかった。
人類が空を手放して百年。自走型要塞都市は地上を止まることなく走り回り、熱エネルギーを循環させながら生き続けている。それでも、全てをSFCだけで補うことは難しい。時折必要なものを供給するために停止し、一定期間、その場で過ごす。抜け殻とはいえ、生前に起因するのか、「餌場」と呼ばれる供給ポイントは、どのサソリも等しく同じ場所を選ぶ。死骸のくせに、そういう鼻は効くらしい。
つまり、生きた巨大昆虫や節足動物との遭遇もあれば、他のSFCと遭遇する場合もあるということ。
激しい資源争奪戦となるのも珍しいことではない。そこで登場するのが、有人型戦闘機となる過去の遺産にして、全知の結晶。空を飛ぶことができる唯一の存在。通称、セルケト。サソリの毒から守る女神の名前らしいが、随分皮肉な名前をつけたものだと、聡夜は月を写す利江娜の瞳を避けながら思う。
有人型戦闘機セルケトの操縦士になることが、聡夜の夢だった。過去形はおかしい。今もなりたいと思い、そうなれるように努力している。
だから、理性が葛藤を生むのだろう。
利江娜の瞳は、夜の月より、晴れた空の下が似合う。どこまでも透き通っていて綺麗な色をしている。
だから、同じ色を持つ空に魅せられたのかもしれない。
本物の空を宿した利江娜の瞳が、夢を夢で終わらせてくれない。
その色が世界で一番美しいことを知っている。
かつて、飛行機、宇宙船。そういう文明が栄えた。人は行きたいときに行きたい場所へ飛び回り、想像もつかない風の感覚さえ知ることが出来たらしい。天災と共に、自然を生きる。自由な空の下で。
「おとぎ話だ」小さな頃、バカにしたように笑った顔は、学校からの帰り道、飛行訓練中のパイロットを見て一瞬で心を奪われた。
あのとき、一瞬だけ見えた青空。セルケトに乗る者だけが行ける自由な世界。
聡夜は、もう何年も同じ夢を抱き続けている。隣に、空の青さを証明する瞳を置いて。
「二十八歳まで受け続けるんでしょ?」
「落ちる前提なのがムカつく」
引き剥がすのを諦めて、再び丘に腰を下ろした聡弥にならい、利江娜も腰を下ろす。
抱きしめた腕を離さなかった意味はない。
お互いに、温もりだけがそこにある。聡夜も利江娜も何も言わない。黙って、夜の静寂に身を寄せ合うだけ。
そろそろ帰らないといけないだろう。
夜が明ければ、日常が待っている。
わかっているのに、もう少しだけ。この時間が続けばいいと思ったのは果たしてどちらだったか。
受験条件に年齢が設けられているのは、それだけ過酷な仕事を物語っているということ。エリートと呼ばれるのも仕方がない。限られた人間、選ばれた人間。優秀な人材の証明。憧れだけでなれる職業ではないからこそ、人は彼らに夢を見るのかもしれない。聡夜と同じく、何年も試みて、結果、一般人として生涯を終える方が何倍も多いのだから。
しかし、一方で、狭き門の恩恵は計り知れない。聡夜の場合は恩恵よりも、飛行への憧れの方に比重があるとはいえ、独り身の母を残すのであれば、恩恵があるに越したことはないとも思っている。
司令塔に入れば、最低十年は出てくることが出来ない。そして、帰れる保証がない。いつ前線に駆り出されるかわからない緊迫感に満ちた職場。置いていく者を気に掛けるのは当然だろう。しかも、近々、サソリは餌場に止まると予測されている。
「いい加減、俺じゃなくて他の男探せ」
「どうして?」
「三十八になってからじゃ遅いだろ?」
「いいよ、別に」
「俺なんか待たなくていいから」
聡夜の呟きに利江娜は何も応えなかった。これが初めてではない。中学二年の夏に告白されたときから、聡夜は利江娜に同じ言葉を吐き続けている。
利江娜が聡夜に伝え続けているのと同じ数だけ。
「………あ」
頭上に歪む月の前を一瞬、なにかが横切った気がした。聡夜のその呟きに、利江娜が顔を向けて、次いで二人揃って瞳に月を戻した瞬間。それは激震を連れてやってきた。
「餌場だ」
非常警報がサソリ内に鳴り響き、静寂な夜が赤いサイレンで染まっていく。攻撃してきたのは巨大昆虫か、同じ自走型要塞都市SFCか。揺れる足場は、聡夜に利江娜を抱き締めることしか許さない。
母親の安否が気がかりだが、サソリは敵を認知して進行方向を変え、爪と尾で威嚇を訴えている。
漠然と、いつ終わるとも知れない夜が始まったのだと悟る他ない。同時に、想定していた以上の現実は、事前告知なく、突然訪れるのだと叩き込まれる。
「………利江娜、無事か?」
「う、うん。あたしは大丈夫、それより聡夜、家に戻………ッ………う、わ」
生き残りをかけた戦いは、体内に宿る住民を気に掛けてはくれない。だからこそ、こういう場合を想定した最深部へ繋がるシェルターの入り口は要所に設けられていた。
「母さんはシェルターに行ってるだろ。俺たちも行くぞ」
「うん」
利江娜を支えながら聡夜も走る。丘のうえから一番近いのは、下った先にある二十五番街倉庫にある。けれど、戦況が均衡しているのか、依然足場は揺れ惑い、大小の瓦礫が頭上をかすめていく始末。
「利江娜」そう彼女の名前を呼ぼうとした刹那、頭上を覆っていた半透明の殻が開く。突風に似た濃厚な風と、静寂を支配する黄金色の月。そして、飛び出していく英雄たち。聡夜の口から出た言葉は、「利江娜」でも「セルケト」でもなく、掠れた息を飲んだ音だけだった。
「利江娜、無事だったのね。心配したのよ。ケガは、してない?」
「ママ、パパ。うん、聡夜と一緒だったから大丈夫。ママとパパも無事でよかった」
シェルターの中に入って、進んだ先にいたのは、都市に住む住民たち。最深部にも居住区があり、各々に集合する場所はあらかじめ、決められている。
聡夜と利江娜も他の住民たちと同じく、指定されたままトンネルを進み、そこで家族と合流を果たしていた。
「母さん」
利江娜と両親が抱き合うのを横目に、聡夜は自分の肉親に声をかける。物言わぬ母親は、青ざめた顔で壁に寄りかかって息を整えているように見えた。
「俺、もう次は受けないことにするよ」
対面一番にそう口にした聡夜の言葉に、ようやく視線が交わる。
「………そう」
どこかホッとしたような、けれど申し訳なさそうな。なんとも言えない顔をしたその身体に、聡夜は手を伸ばそうとして、止めた。
手には赤黒い液体がこびりつき、ところどころ鉄臭さが鼻につく。それは、セルケトがもたらした血の雨であり、攻撃を仕掛けてきた要塞都市に住む人々の雨だった。
敵側の心臓を尾で一突きして勝利を得たのは、聡夜たちの暮らすサソリの方で、次はいつ自分達がそうなるかわからないほど、一瞬で呆気ない終焉だった。
「定食屋、継いでいいかな?」
「あんたが継いでくれりゃ、亡くなった父さんも喜ぶよ」
「………贅沢、させてあげられないけど」
「望んでないって、父さんもそう言ってたろ?」
「………うん」
夢は夢だからこそ美しい。
多くの人がそうであるように、聡夜も一般人になる道を選んだだけのこと。今、このときも。聡夜が憧れた英雄たちは、暗闇の世界で生温かな雨の中、資源を物色しているだろう。
そうしなければ、生きていけない。
繰り返されてきた歴史は、状況を変えて繰り返されるだけ。明日、自分達がそうならない保証はない。
「で?」
「ん?」
支え起こした母の口から出た質問がわからず、聡夜は首をかしげる。「鈍い子だね」と呆れた顔をされたが、わからないものは仕方がない。
「利江娜ちゃんにプロポーズ」
「は!?」
顎で促される意味がわからない。言われた意味を理解して、瞬時に顔を赤く染めた聡夜の叫びに、何事かと利江娜が両親を引き連れたまま近付いてくる。
このタイミングで、やめてほしい。
聡夜がそう思ったかどうかは定かではない。けれど、いつも状況は自分を待ってはくれない。立ち向かうしかない。
「聡夜、どうかしたの?」
憧れた空の色が、触れるほど近くに寄ってくる。心配そうに覗き込む利江娜の瞳を見つめて、それから大きく息を吸って、聡夜は赤い顔のまま、格好のつかない告白をした。
「あのさ、一緒に定食屋してほしいんだけど」
「………え?」
互いの両親が見守るのだから、そこから先は難しいことはない。それでも最初の一歩を踏み出すには、相応の緊張が付き物で、聡夜も例に漏れずそれを感じている。
高鳴る心臓の音は、ケガの無い身体にも痛みを与えてくる。呼吸が苦しい。
中学二年の夏。目の前の相手がこの思いをしていたのだと思うと、余計に愛しさが込み上げて、泣きたくなるほど思いが溢れた。
「え、聡夜。なに、どうして、急に」
「俺と結婚してください」
勢いよく頭を下げた聡夜は知らない。
疑問符を浮かべていた利江娜の瞳が、理解不能に瞬いて、それから徐々にその表情を崩していく。
静まり返った空気が、成り行きを見守っている。
八年間伝え続けられた「好き」の言葉。返事は、聞かなくてもわかっていた。それでも実際に、利江娜の声を聞くまでは、不安でたまらない。頭を下げたままの聡夜は、口から心臓を吐き出さないことに精一杯で、空の色を宿した瞳から雨が落ちることに気付かない。
夢を追いかけたとしても、利江娜は変わらず傍にいてくれただろう。
夢を叶えた先は、わからない。
青い空の下を自由に飛べることを今はもう素直には喜べない。聡夜は、知ってしまった。
自分にとって大切なもの。一瞬で心奪われたのは空の青さではなく、その色を持つ瞳だったこと。
生きる場所が変わっても、人間は変わらない。等しく生きて、死んでいくだけ。それを「愛」と呼ぶならば、赤い色で染めるのではなく、青い色に染まりたい。
かつて憧れた夢と同じ、いつまでも色褪せない空のなかで。
(完)
あとがき
ファンタジーが大好きなので、素敵な企画に飛び付いた形となりますが、意外とドラゴン以外の怪獣とか巨大生物が出てくる物語を書いたことがなかったことに気付き、筆を取ってからしまったと血の気が引いたのは秘密です。とはいえ、かなり楽しませていただきました。
ありがとうございます。
心情描写よりも風景描写の方が好きなので、空や色を引き合いに出すのが多いです。
普段は大人女性向けの小説を書いているため、かなり系統が違うものの、恋愛要素が入りました。すみません。もっと戦闘を入れたかったのですが、永遠に続きそうな気がして、私なりの終着点を見つけた結果です。
こうして、狭い世界の話を書いていると、自分は随分と恵まれた世界に生きているのだなと思います。風を感じて、空を見上げて、当然のように与えられた世界をもっと楽みたい。そうして、全部を糧にして、これからも架空の物語を具現化させて、楽しんでいきたいと思います。

プロムナードとは
遊歩・散歩を意味するプロムナード。「日常の中にほんの少しの非日常を」というコンセプトを元に、短く仕上げた物語たちのこと。皐月うしこオリジナルの短編小説置き場。
※文字数については各投稿サイトごとに異なる場合があります。
※読了時間については、1分あたり約750文字で計算しています。