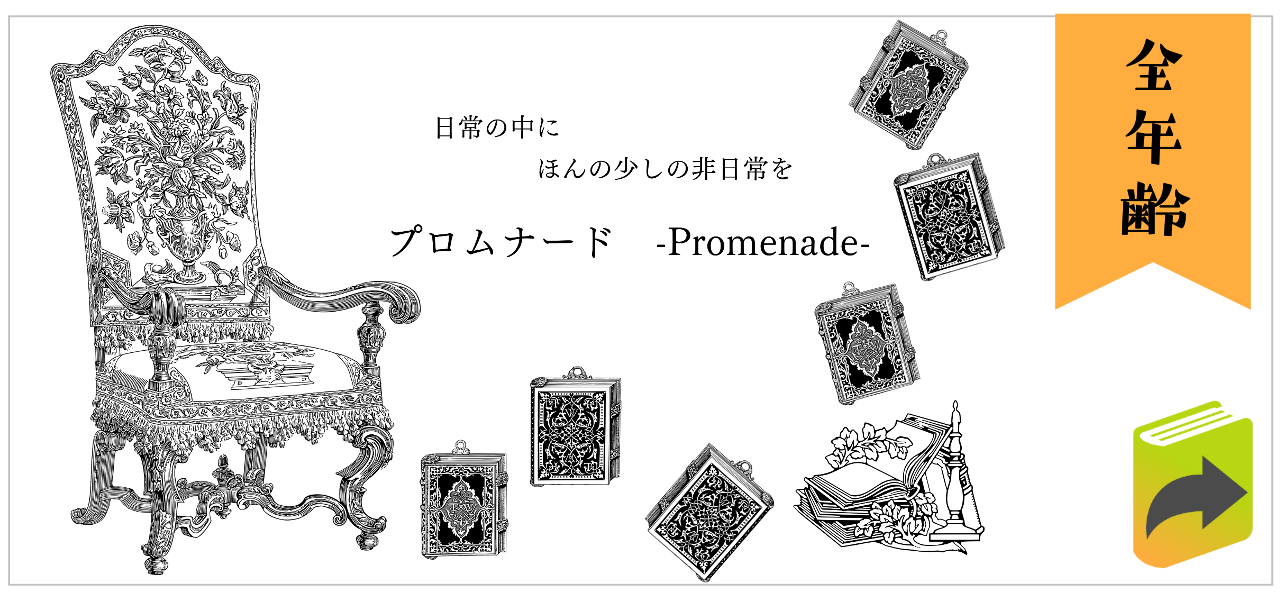短編「我が潮騒の恋慕」
概要
2016年に公開した作品を移行したものとなります。
我が潮騒の恋慕
読み:わがしおさいのれんぼ
公開日:2016/10/09
ジャンル:和風ファンタジー
文字数:約8900字
読了時間:約12分
タグ:切ない/悲恋/身分差
本編「我が潮騒の恋慕」
これで良かったのです
だからどうか忘れてください
貴女様と過ごした日々は
私の胸の中だけでいつまでも
色褪せることなく思いましょう
いつかくる宿命と知り
ずっと ずっと
今日という日が来ることを
覚悟しておりました
さわさわと流れる風が心地よく肌を撫でていく。
鼻腔をくすぐる潮の香りと波の音。
目を閉じれば穏やかな眠りへと誘われる太古の囁き。
「また、このような場所で」
砂浜を踏みしめるようにして現れたその声の主は、目当ての人物を見つけてその顔をほころばせた。
漆黒の袴に落ち着いた藤色の衣が美しく、結わえた髪の上に被せられた黒の帽子が落ちないように紐でアゴへとくくられている。
「鈴那姫」
その心地よく響く低音な呼び掛けに応じれば、きっと誰もが息をのむだろう。
艶やかな長く美しい髪が揺れ、薄紅の衣をまとった女神が振り返る。
長い睫毛に黒塗りの瞳。
滑らかな白い肌と儚い面影。
今まさに海の中から誕生したと言われても誰もが首を縦に振って了承するほどの美貌がそこにはあった。
「そなたか」
幼い色気はどことなく危険な匂いを漂わせ、可憐な声は波に紛れて吐息となって消える。
幾人もの女性を抱いてきた男でさえ、恐れ多くて手が出せずにいることをきっと彼女は知りもしないだろう。
「なにようじゃ?」
鈴那(すずな)は薄い眠りから覚めるようにパチパチとまばたきをしながら目の前の男に問いた。
記憶が正しければこの男は先日、自分の身の回りの世話にとあてがわれた使用人のはず。
今までの世話人は年をとり、お役御免となったらしく、この目の前の男と入れ替わるようにしてどこかへと帰っていった。
「世話がやけますな」
男は大抵の女ならば赤面して顔をそらせるような眼差しを向けて、鈴那のもとへと近づいてくる。
苦笑して吐き出された息とは違い、その双眼には愛しさがにじみ出ていた。
「イヤなら辞退すればよかろう」
鈴那はふんっと鼻を鳴らして、再び波の音へとその身をゆだねる。
ひいては返す海の音色が穏やかにゆっくりと黄昏時の空を歌っていた。
海の底へと潜っていくように、その水面に溶けていく茜色が実に美しい。
「美しいですね」
自分と全く同じ感想が隣に立つ男の口から聞こえたが、鈴那は無視することにして太陽の行方をじっと見つめていた。
別に共感などいらない。
この景色の美しさは、語らずして目に焼き付けるものだと思う。
どこか遠い土地に行ったとしても、まぶたを閉じるだけで思い出せるように。
「して、なにようじゃ?」
一向に問いかけに応じない男へと鈴那は声だけで尋ねる。
隣の美男はふっと口許を緩めると、その問いに答えるように体を鈴那の方へむけた。
「いいえ、何も」
キラキラと赤く彩られた水面とは対照的な冷めた視線が鈴那から放たれる。
「用もないのに、わらわを探しておったのか?」
皮肉を込めて少しだけ顔をむけて見たが、案の定、彼は何の打撃も受けていない平然とした顔でうなずいた。
「はぁ」
どうしたものかと、鈴那の口からため息がこぼれ落ちる。
苦手だ。
初めて会ったときから、この男はなんだかとても苦手だと感じていた。
特にイヤなことをされたわけでもなければ、初見で人にそういう感情を抱いたこともない。
以前の世話係も男だったので、特に彼が初めて接する異性というわけでもなかった。
「夜になる前に帰りましょう」
手を引いて立たせてくれる目の前の男は、別に態度が悪いわけではない。
むしろ良すぎるくらいだ。
真綿をくるむように大事に扱ってくれるし、細かなことに気が回せるし、公平に接してきて嫌味もない。
位の高い身分にありながら腰も低く、その秀麗な容姿に甘んじることなく、学問を積極的に学んでいる。
数日観察してみたが、ある一点をのぞけば文句のつけようがなかった。
実に苦手だ。
「なにゆえ」
この男であれば引く手数多(アマタ)だったことだろうと思う。
何も辺鄙な土地の海辺に住まう娘に仕(ツカ)える必要はなかっただろう。
「鈴那姫、どうかなさいましたか?」
突然心配そうに顔を覗きこんできたせいで、物思いにふけっていた鈴那はビクリと肩を震わせて足を止めた。
砂の上を引きずる衣がその動きに合わせて波紋を描く。
「なんでもない」
ぎこちない声で小さく否定した鈴那は、その男の顔から離れるように再び歩き出す。
なぜか、ドキドキと胸の鼓動が早く脈打っていた。
うるさい。
この男が傍に来るようになってからというもの、鈴那の日常は穏やかとは程遠くなっていた。
この男が来るまでは静かな波の音と贅沢の中にも質素な生活に満足して、年老いた世話役と二人、ゆっくりとした時の中を生きていた。
「はぁ」
帰宅するなり、食事の支度をするからと男が部屋を出ていった途端、鈴那の口からは安堵の息が盛大に吐き出される。
「生きた心地がせぬ!」
きつく締め上げられていたのではないかと疑う着物はいつもと何ら変わらず、落ち着くために座ってみれば疲れがどっと押し寄せてくる。
なぜかはわからない。
男が来てからというもの、息苦しさと窮屈さは日を追うごとにひどくなっていた。
「何ゆえ、あのような者がわらわの世話をする羽目になったのだ?!」
はぁはぁと、鈴那は苦しむ胸を押さえながら忌々しそうに独りごちる。
ここ数日考えてはみたが、結局答えが見つからなかった疑問が頭に浮かんでは渦を巻いて鈴那を悩ませていく。
空はいつしか夜が広がり、太陽に変わって美しい月が出ていた。
「はぁ」
少しホッとする。
穏やかな月の明かりと眠る前の夜の波音は、激しく脈打つ鼓動を押さえてくれる作用を持っているに違いない。
そうして人知れず大きく深呼吸した鈴那は、男が食事の支度をしているのをいいことにボーッと月を眺めることにした。
「月はよいな」
人工的な明かりがない室内にもその崇高な光は、ほどよく届いている。
淡く優しい眼差し。
部屋に一人座って見上げる月は、自然と気持ちを穏やかにしてくれる。
「落ち着く光じゃ」
目を閉じてうっとりと鈴那は吐息をこぼす。
この感覚が一番好き。
やはりあの男がいることで乱される感覚は、どうしても好きになれそうにない。
自分に合っているのは平凡で変わらない時間を送ること。
「そのように私も見つめられたいものです」
「ッ?!」
いつからそこにいたのか、数刻の間、無警戒の体制で月を見上げていた鈴那は、面白いほど狼狽したようにわたわたと辺りを見渡した。
それにクスクスと笑い声をこぼしながら、男は配膳を持ったまま室内へと足を踏み入れる。
「月に妬けます」
優雅な所作で鈴那の前にお膳を置いた男は、目線を合わせるようにして微笑むと何の断りもなく鈴那の脇へとその腰をおろした。
「お主は口が軽い」
鈴那は変な動悸を探られないように、わざと淡々とした口調で彼の視線を誤魔化した。
どうしても冷たくなってしまう声色に若干後ろめたさを感じながらも、鈴那は目を合わせるのを避けるようにお膳へと顔を向ける。
「相変わらずだな」
なんでもこなせそうに見える彼も料理はなぜか壊滅的によろしくない。
お世辞にも美味しそうだとは言えない見映えと味に、鈴那は顔をひきつらせながら喉の奥でうーんとうなった。
「よくこれで世話役になれたものだ」
どういう仕組みで自分の世話役が決定するのかはわからないが、一日の中でも極めて重要な栄養源がこの調子では鈴那も長生きは難しい。
いや、望んで長生きしたいわけではないが、この男の料理を食べ続けていれば間違いなく三日はもたないだろう。
「少し待っておれ」
鈴那は困ったように小さく息をついたあと、おもむろに立ち上がって悲しそうに瞳を伏せる男の横を通りすぎる。
通りすぎるときに感じたわずかな香りが胸の高鳴りを引き起こしてきたが、鈴那はあえてそれに気づかない振りをして台所まで足を運んできた。
「これではどちらが世話をやくのかわからぬな」
鈴那はやわらかな着物の裾をまくって、その細い腕をくるくるとまわす。
そうしてものの数分で、鈴那は二人分の食事をこしらえた。
「どっどうじゃ?」
自分の料理を他人に振る舞うのは初めてなだけに、妙な緊張感が鈴那を襲う。
前の世話役であった翁に料理は教わったが、前任者は年こそ老いていたものの非の打ち所がないほど完璧な世話役だったので鈴那の活躍はないに等しかった。
それに比べて、目の前の美しい男は鈴那の料理を嬉しそうに頬張っている。
始めこそ驚いた顔をしていたが、恐る恐る口にしたその味を確認するや否や無言で食べ進めているのだから感心する。
「美味しいです」
その笑顔で何人の女を落としてきたのかはわからないが、ペロリと平らげた彼の様子を不安そうに見つめていた鈴那は、その返答を受けて嬉しそうに微笑んだ。
「よかった」
不味いと言われたらどうしようとか、無理して食べていたらどうしようとか、柄にもなく不安が心を支配していた。
おいしいと、その一言がこんなにも嬉しいものなのかと、鈴那は払拭した不安を喜びに変えて笑顔になる。
その顔を男はじっと見つめていた。
月に照らされた天女のような美しい姫が嬉しそうに笑う姿に、心が奪われない者がいるなら会ってみたい。
そう思うほど鈴那を愛しいと感じる欲情が理性を奪おうとするが、男は胸の奥にある痛みを隠すようにギュッとその拳を握りしめて耐えていた。
相手は姫。
一時の感情や、その場の雰囲気で押し倒していい相手ではない。
「鈴那姫さま」
男は感情を取り消すように咳払いをしたあと、優越に笑う鈴那の名を呼ぶ。
「食事はわらわに任せるがよい」
どう見ても照れ隠しにしか見えない咳払いに、鈴那は男の顔を覗きこむようにして笑った。
この澄ましたような秀才に、ひとつでも勝てることがあるのかと思うと妙にくすぐったくて嬉しくなる。
「よいな」
そう命令した声は、恍惚に弾んでいた。
「仰せのままに」
敗北を認めて頭を垂れる姿にはゾクゾクと言い知れぬ感情を鈴那に与えてくれた。
それからと言うもの、主従関係の境界線が薄れたように思う。
得意なことは得意な者が率先して行い、苦手なものは二人で共同しながらこなすようになっていた。
姫と世話役という立場は忘れてはいないが、仲裁役がいるわけでもないため、二人は同居人として上手く役割を分担し始めていた。
そうして一ヶ月がたった頃、突然それはやってくる。
「姫様、文が届きました」
気心は知れたものの、相変わらず彼が傍にくるだけで変な動悸や息切れが頻繁におこる。
息苦しさや緊張感も特に収まったわけではない。
けれど、言い知れない信頼と安堵がそこには存在していた。
「読んでたもう」
「なりませぬ」
髪をとかしていた手を止めて、鈴那は世話役へと顔をむける。
即座に否定された物言いに一抹の疑問を感じながらも、鈴那は仕方なくその手紙を彼の手から受け取った。
厳重に折り畳まれた白い紙。
しなやかな指先でパタパタとそれを開いて読み始めた冒頭に、鈴那は目を見開いて息をのむ。
「なるほど」
そこには、姫であるがゆえの宿命が記されていた。
「わらわもついに、嫁ぐことになった」
ふっと自嘲めいた笑みがこぼれるのも無理はない。
「何年も放置し、人目を避けるように隔離して庇護された娘が今さら公の場に出てなんとなるというのか」
父も母も、もう何年と会っていない。
物心つく頃から世話役だった前任の翁と二人、他人の介入を許さない辺鄙な土地で人知れず静かに身を潜めていた姫の存在など、とうの昔に忘れ去られていると思っていた。
いや、思い出したのかもしれない。
翁の死と同時に娘がいたことを。
「お主、名はなんという?」
鈴那は文を握りしめながら抑揚のない声を傍(カタワ)らに控える男へと投げ掛ける。
この一ヶ月半。
名前は聞いたことがない。
二人しかいなかったので特別不便に感じなかったことも大きいが、聞いてはいけない何かがそこにはあったように思う。けれど、今ここでその名前が知りたいと鈴那は男の双眼をとらえるように顔を向けた。
「答えられませぬ」
「そうか」
寂しくにじむ鈴那の声は室内に溶けて消える。
別に婚礼は珍しいことではない。
顔も知らない殿方の元へ嫁ぐことは、姫として生まれた以上、いつかくる宿命であるとは思っていた。
ならば、と鈴那は顔も曖昧にしか思い出せない両親を恨んだ。
「世話になった」
文に書かれた名と彼の名が同じであればと、束の間に願ったことは胸の内に隠さざるを得なくなった。
もう二度と会うことはない世話役を用意する前に、誰かに嫁がせてくれたらよかったのに。
名前も知らない男との暮らしが永遠に続けばいいのにと思う前に、この文を届けてほしかった。
「一人にして」
消えそうなほど下を向いてその手紙を握りしめた鈴那に、男は何か言いたそうに口を開いたが、結局その口から声は紡がれることなく、代わりに部屋からその男の足音が静かに遠退いていった。
しんとした部屋に、海の波音だけが虚しく響く。
寄せては引いてを繰り返す無限の音。
日常の一部でもあったこの音色さえ、もう二度と聞けないかもしれなかった。
「ッ?!」
耐えきれず鈴那は突然走り出す。
「鈴那姫?!」
後ろから抱きつくように突進してきたかと思ったら、そのまま押し退けるようにして走っていった後ろ姿に男は驚いた声をあげる。
見慣れた薄紅の羽織を揺らしながら飛び出していくその背中に手を伸ばして引き止めることは、どうしても出来なかった。
ドンッと男は壁を叩く。
パラパラと漆喰が剥がれてこぼれてきたが、気にもせずに男は人知れず大きく息を吐き出した。
「くそっ」
鈴那の行き先はわかっているので、心配はしていない。
祖父から繰り返し聞いた姫の行動は、一緒に住んでなお、容易に想像できる。
今、問題なのはそちらではない。
「鈴那様」
名前を口にして、より深く知る。
初めは世間知らずのわがまま娘だと変な先入観と思い込みがあった。
その美貌を鼻にかけ、男なら誰でも命令すれば言うことを聞くとでも思っているのだろうと半ば決めつけていたのも否定はしない。けれど、一緒にいてそれが違うことに気づいた。
ただの世話役のくせに、祖父が孫のように溺愛していたのがよくわかる。
素直に顔に出ているのに口では逆のことをいって強がり、色んな物に興味を示して楽しそうに笑う姿は幼く、かと思えば月や海を見つめて吐息をこぼす姿は見惚れるほどに美しく色気があった。
一番年が近いからと、ふらふらと遊んでいた息子を心配した父が勝手に決めた仕事だったが、彼は鈴那の世話役に任命されたことを今では誇らしいと感じてすらいた。
「わかってはいたのに、これほどとは」
初めから三ヶ月あまりの任期だということはわかっていた。
彼自身、それ以上の仕事であれば初めから承諾はしなかっただろう。
条件はただひとつ。
互いの記憶に残らぬよう勤めること。
姫はあまりの美しさゆえ、内密に育てられた花。
幼い頃より近隣の大名に目をつけられ、誘拐未遂は何度もおこり、物心つく前から婚姻の申し出は他方に渡って迷惑きわまりなかった。
娘の行く末を案じた鈴那の両親は、信頼できる彼の祖父に人里離れた辺鄙な土地で大切に育ててほしいとその命を託した。
それでも生家に連日押し寄せる文や贈り物はやまない。
姫をどこに隠したのかと脅迫めいた事件まで起こっているのだから驚きである。
「鈴那さま」
一五になるまで、残り一ヶ月半。
彼女の両親はついに、伴侶となる男を決めたのだ。
どれだけ思いを馳せようと、それは叶わない恋慕。
「わらわは、ここしか知らぬ」
潮の香り、どこまでも青く続く水平線の向こうは、どちらが先に誕生したのかわからない空と海が混ざりあっている。
白い雲と泡立つ波線。
境界線こそあるものの、その壮大さはすべてを包んで洗い流してくれるようだった。
「わらわは、翁とお主しか知らぬ」
海岸沿いに立つ一本の松の木。
その木陰がお気に入りの場所。
何かあれば必ずここに来て海を眺め、うとうとと眠りにつく鈴那を迎えに来てくれたのは人生でたった二人だけ。
「その二人の名も知らぬ」
なぜこんなにも悲しいのかは、自分でもわからなかった。
永遠にこの地にいると、どこかで思っていた。けれど、自分がそれ相応の身分である自覚は持っていたため、いつかこんな日が来るであろうとも思っていた。
どちらでもよかった。
今までは────
「また、このようなところで」
────この男と出会うまでは。
苦笑混じりの顔で隣に腰かけて、同じ海を見る男と出会ったのは一ヶ月半ほど前。
体調を崩した翁が何を思ったのか、自分の後継者にと孫である彼を連れてきた。
その姿を一目見たとき、鈴那の胸には一種の感情が生まれた。
「お主とおるとな、わらわは緊張して上手く話せぬし、些細なことで心臓も早くなり、体も熱くなるのだ」
「はっ?」
少し困ったように吐露した鈴那の心情に、驚いた男の顔が風にあおられるように動く。
「誠にございますか?」
「いや、普段はいたって大事ないのだ。そのように顔を近づけられたりすると……その…っ…ほら」
両手で牽制するように振り返った男を拒みながら、鈴那はその体を少し横に遠ざけた。
あれだけ聞こえていた海の音が消える。
ドキドキとうるさくなった心音に、不可解な感情がまた込み上げてくる。
うるさい。
「鈴那様」
「ッ?!」
その低音は波の音より心地よく、海より深い眼差しと、空よりも清々しい雰囲気が優しく鈴那の名を呼ぶ。
「大丈夫です」
牽制していた両手を握られ、その手に唇をあてる顔は美しい。
「私のことなどすぐに忘れます」
見上げられた瞳とその悲しそうな言葉に、心がズキリと痛んだ気がした。
忘れるのだろうか。
「嫁がれるまでの残り一ヶ月と少し、きちんとお世話をさせていただきます」
そう言って頭を垂れる彼にかける言葉は、何ひとつ見つからなかった。
ああ、本当なのだなと沸かなかった実感がほんの少しだけ、鈴那の心に陰りを落とす。
それからの一ヶ月はどう過ごしていたか、確かな記憶は残っていない。
記録もしていない。
毎日のように海を眺め、見納めのようにカモメの歌を聞いて、夜の月をうたった。
もう二度と見ることはないだろう。
「鈴那、大きくなって」
嬉しそうに涙ぐむ年配の女性は、ほとんどうろ覚えの母でしかなく、何も心が動かない。
綺麗な人だなと思うが、それ以上でも以下でもなく、鈴那は曖昧な笑顔を作ってうなずいた。
「お久しぶりです。母上」
婚前の衣装は上等な質の良いものが用意され、頭や首につける宝飾品も見たことがないほどきらびやかな物ばかり。何十人といる使用人たちは能面を張り付けたように黙々と豪華な屋敷の中を往復しているが、誰もそこにいないような空気が漂っている。
息がつまりそうだった。
「おお、息災であったか」
「お久しぶりです、父上」
部屋へズカズカと大股で入ってくるなり、大声で乱雑に腰をおろした相手へと鈴那は両手をついて頭を下げた。
「よい、面をあげよ」
「ありがたく存じます」
顔をあげた鈴那に、父と名乗る男がハッと息をのむ。
妻へと声をかけようとしていた顔が石膏のように固まり、ごくりと唾を飲み込む音が聞こえた。
「あなた様!?」
「お…おお、すまぬ」
妻にたしなめられて動き出したぎこちない男は端正な顔立ちで数回うなずいたあと、場をとりなすような咳払いをひとつして姿勢を正す。
「大きくなった」
「はい」
「美しくなった」
「はい」
なんなんだこれは。
単調にしか言葉をかけれないらしい父らしい人物に顔をひきつらせながら、鈴那はにこやかに返事を繰り返していた。
ここが生まれた場所だと言う実感が少しもわいてこない。
確かに言われてみれば似ているかも知れないが、目の前の男女に思い出もないに等しく、鈴那は勤めておしとやかに座っていた。
仮に情を思い出したとしても、すぐに別れるのだ。
何もない部屋の向こう側には、今後の人生を共に過ごす顔も名前も知らない殿方がいるだろう。
「皇子をもうけ、后として───」
つらつらと、言葉を続ける親の顔はとても嬉々として弾んでいる。
娘が嫁ぐ先が余程お気に入りとみえる。
「───皇子、日の本を統べる天皇家の者だ」
「はい」
それがどれほどすごいものなのかは知らない。
流れていく中で実感を得るのかもしれないが、鈴那にとってそれは不安と疑心しかない暮らし。
帰りたい。
そう思える場所はたったひとつ。
「まだ、慣れませぬか?」
嫁いだ先で、夫と呼べる人物はとても優しく良くしてくれた。
不自由など何一つない。
鈴那のまわりにはいつも愛で溢れ、その美しい姿を一目見ようと人で溢れている。
献上品も毎日のように届けられ、たまに夫が嫉妬するくらいだった。
「いえ。ただ懐かしく思っておりました」
ここには潮の香りも、寄せては返す波の音もない。
けれど、見上げる夜空の月は同じ。
「そうだ、これを」
「これは?」
愛しい妻へ、出来ることなら何でもしたいと皇子は誇らしげにそれを鈴那へ手渡す。
真っ白な渦巻き貝。
海の産物であることは確かだが、これを一体どうしろというのか。
「耳に当てると海の歌が聞こえるそうな」
「海の音が?」
鈴那の顔がわずかに色づく。
あの場所を離れて五年。
怒濤のような都暮らしに、ようやく慣れ始めたとはいえ、心労は確実に鈴那の身体を弱らせていた。
今では儚さに拍車がかかり、今にも消えてしまいそうな危なげな魅力が鈴那を包んでいる。
「まぁ」
耳に押し当てて愛しそうにまぶたを閉じる鈴那の瞳に涙がにじむ。
聞こえる。
懐かしい音が、かすかに耳に届いてくる。
「ありがとうございます」
そう言って微笑む鈴那に、皇子は満足そうにうなずくと、身体に障りがあってはいけないからと部屋を出ていった。
彼が愛しくないわけではない。
心温まる日々を過ごさせてもらっていることは、幸せともいえる時間だと思う。
「はぁ」
けれど、思い出さずにはいられない。
激しく波打つ鼓動を引き起こすのは、あとにも先にもたったひとり。
名前も知らない彼は元気だろうか。
あのときは幼くわからなかった気持ちが、今では痛いほどに理解できる。
もう一度戻れるなら、歴史には描かれない暮らしがしたい。
あの穏やかで、いつまでも続く場所で、誰にも邪魔されない時間を過ごしたい。
「また、このようなところで」
彼の声が聞こえてくるようだった。
その声でもう一度名を呼んでほしい。
そうすればきっと、今度こそ。
「お慕いしておりました」
叶わぬ思いの先に映る幻想に、鈴那は波の音を聞きながらそっと瞳を閉じた。
(完)

プロムナードとは
遊歩・散歩を意味するプロムナード。「日常の中にほんの少しの非日常を」というコンセプトを元に、短く仕上げた物語たちのこと。皐月うしこオリジナルの短編小説置き場。
※文字数については各投稿サイトごとに異なる場合があります。
※読了時間については、1分あたり約750文字で計算しています。