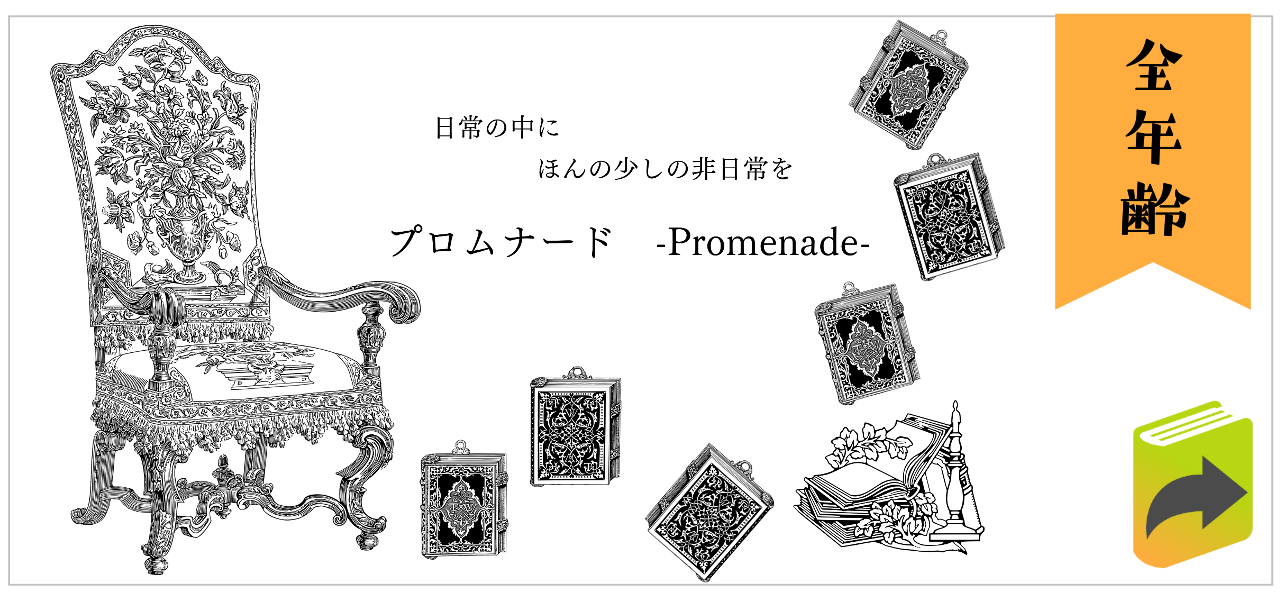読切「三匹の黒猫」
概要
2018年5月に刊行された星空ヱトランゼ様主催の「おやすみ前に読む合同誌『Dream Lantern』」参加作品となります。
》》寄稿詳細はこちら
三匹の黒猫
読み:さんびきのくろねこ
公開日:2019/08寄稿
ジャンル:ファンタジー
文字数:約3300字
読了時間:約5分
タグ:少女/黒猫/魔法/古城/物語/夜
本編「三匹の黒猫」
眠れや眠れ愛しい瞳
白紙のページに描かれた
物語はまだ終わらない
今夜も詠み聴かせましょう
かつての栄光と称賛を
与えられた恩恵の上で
あぐらをかいた愚かさを
いつか思い出すその日まで
いつか気が付くその日まで
子守唄は魔法の詠唱
愛しい愛しい王子様
眠れや眠れ夢の国で
どこか遠くの方で時計の針が真夜中を告げている。
低い音は十二回の鐘を鳴らしているが、静寂が支配した屋敷の中でその音を楽しむ者は存在しない。
ギシッ
足元さえ怪しい暗闇の中で床の軋む音がわずかに聞こえ、次いで、ぽぅっと優しい光がある一点に集中した。
「あら、お早いお越しですこと」
床に小さなランタンを灯した少女は、その明かりの中に見えた三つの影に頬を緩ませる。にゃーっと可愛い泣き声がして、三匹は少女の周りで共通の仕草を見せた。
青い瞳、赤い瞳、黄金の瞳。瞳の色が違うだけで、他はそっくりな三匹の黒猫。
「待って待って、私は仕事を終えたばかりなのよ」
せがむようにそれぞれの色で見つめてくる三匹の熱意を受けながら、少女はまたくすりと笑う。毎晩のように〝こう〟ではたまらない。けれど、これは三匹が猫として生きるようになってから幾度となく繰り返されてきた日課。今更、辞めるわけにはいかない。
「仕方ないわね」
少女はボロボロの仕事着のまま、簡素なベッドの上に置いてあった一冊を手に取って床に座る。
「それでは今夜もようこそいらっしゃいました」
少女が恭しく頭を下げると、三匹の猫は一度顔を見合わせてから、思い思いの体制を整え始めた。一匹は少女の前でピンっと胸を張り、一匹はランタンの傍でくるっと丸まり、最後の一匹はベッドの上から少女の背中へ身を寄せている。ほとんどが黒に染まった三匹でも、性格は三種三洋。
今夜の居場所が決まったところで、少女は手に持っていた本をぱらりと一枚捲り始める。
「むかしむかしあるところに……」
これは、白紙の本に描かれるどこにもない物語。
少女の声だけが語ることの許された一夜限りの朗読会が始まった。
「むかしむかしあるところに、見目麗しい三人の王子様がおりました」
* * * * *
天高くそびえる巨大な城は美しい山と川の中腹にそびえたち、行商人の行き交う中間地点の国として、それは見事な繁栄を誇っていた。途切れない物資、異国の珍しい品々、恵まれた環境。そして何より人々の目を惹いたのは、この国に存在する「魔法」と呼ばれる特殊な力の存在だった。
「王子様だ!」
「王子様たちがご帰還なされたぞ」
人々の歓声に目を向けてみると、凱旋から帰還したらしい三人の王子がそれぞれ率いる軍の進行が見えた。巨大な正門の先から城に向かって、眼下の民には目もくれずに、馬にまたがったまま王子たちは進んでいく。
その勇姿たる横顔を拝もうと、周囲は人垣となり、思い思いの声を叫んでいる。
王子様、おかえりなさい。王子様、王子さま、おうじさま、オウジサマ
手を上げ、瞳を輝かせ、自分たちには見向きもしない王子相手に、群衆は敬愛の眼差しを持って彼らが城へ帰っていくのを見守っていた。
「王子様、今日もカッコよかったわ」
「見たか、セシル様が持っていらしたあれは竜の爪だ」
「見た見た。ガザエル様が首からかけていたのは新月の鏡に違いない」
「それよりもティール様が運んでいらしたあれって」
「ああ、今回も討伐の目的を果たされたのだ」
「さすが王子様だわ、この国も安泰ね」
「王子様、万歳」
「王子様、万歳」
人々の声は帰還した王子たちをたたえて夜の祝宴会へとなだれ込んでいく。国の平和は王子たちがいる限り永遠に安泰だと、誰もが口々に笑みを浮かべ、安寧の未来を祝福して乾杯の音頭を謳っている。ところが、打って変わって彼ら三人の王子が帰還した場内は険悪なムードが漂っていた。
「冗談じゃない」
馬から降り、玉座での謁見が終わった三人は父親である王が席をはずすなり、輪になるようににらみ合っていた。
青い瞳のセシル王子。
赤い瞳のガザエル王子。
黄金の瞳のティール王子。
この国で有名な三つ子の王子は、瞳の色が違うだけで見目はとても良く似ている。流れる漆黒の髪と、漂う色気と整った顔立ち。幼いころは仲が良かった三人も年齢を重ねるにつれて、次期玉座を巡る争いに身を投じていた。
「今回も誰も王には決めないとはどういうことだ」
吐き捨てるような苛立ちのまま玉座の間にその声が響き渡る。
「俺の仕留めた竜の大きさをお前たちも見ただろう」
セシルが怒りに任せて自分の腕よりも太い竜の爪を床に投げ捨てる。ガランと重力に沈む音が大理石の床を欠けさせたが、セシルは気にしないといった風に、その青い瞳を残りの二人へと向けた。
「竜など問題ではない。わたしのもつ新月の鏡が今回の勝利の要だった」
ガザエルが首から下げた黒い鏡を二人に見せつけるように両手で持つ。真っ黒な円盤にしか見えないそれは、何も映しはしなかったが、ガザエルの手の中で暴れるようにガタガタと不気味に震えていた。
「わたしの力が鏡の力を抑えているから作戦はうまくいった」
「それはどうかな」
ガザエルの言葉尻を捕えるように、ティールがニヤリと挑戦的な笑みを浮かべる。次いで、どさりと床に何かを転がした。
汚れた白いボロキレは、よく見ると人型をくるんでいるような形をしている。いや、よく見なくてもそれは紛れもなく一人の人間をくるんでいた。
「最終的に魔女を捕えたのはこの僕だよ」
ティールが勢いよく剥がした白い布の中には意識を失った少女が一人。
可哀そうに傷だらけの上に、腕や足に鎖が取り付けられているが、眠ったように横たわるその顔は玉座を約束された戦利品の一つとして、当然と言えば当然の有様なのだろう。
「これで僕が玉座に一歩近づいたね」
「はぁ、ふざけるな」
「それを言うならこのわたしだって」
ぎゃーぎゃーと騒がしい口喧嘩は今に始まったことではない。城下の町に住む人々は表の顔しか知らないだろうが、近頃の王子たちは何かと一番を競って言い争いを繰り返していた。
現王はそうした兄弟の不仲を憂い、折を見ながら課題を与えて試練を乗り越えさせるのだが、王子たちは勝利をおさめこそすれ、仲を深めることはなかった。むしろ亀裂が深まっているといっても過言ではない現状に世界が困惑していることなど、彼らは露ほども知らないだろう。
「あわれだな」
三人とは違う声が、大理石の床から零れ落ちる。
「はぁ?」
ここはさすがというべきか、声のそろった兄弟仲に囚われた傷だらけの少女の唇が嘲笑の息を吐いた。
「貴様らの不仲のせいで、周囲の環境が悪くなっているとも知らずいい気なものだ。遊び感覚で森を焼き、空を焼き、古の竜を殺し、魔法を乱雑に扱う。治める国、称える民があれど、貴様らの内、誰が玉座についたとしても歓迎する神はいない」
ぐっと少女が唇を噛み締め、顔を歪ませる。三人の足が同時に少女の上にのしかかったからだが、少女は一瞬の苦悶を浮かべたあとは、実に平然と言葉を続けている。
「静かに暮らしていた私を捕えたところで、それが貴様らの玉座戦争にどう影響した?」
問いかけには誰も答えない。
「王は望んだ。このままでは我が息子たちが世界を滅ぼすのではないかと案じた」
視界はいつも、みたい世界しか見ようとしない。城下町に暮らす民は盲目的に自国の王子を讃えているが、魔法で美しく見せられた世界の周囲は、変化に苦しみ喘いでいる。都合よく描かれた物語の主人公になって、物事の本質には無頓着でしかない。
「力の誇示は己の称賛を得るために使うものではない」
少女の声に力がこもる。
「そのまま足を乗せているがいい。愚かな王子たちよ。与えられた世界でしか生きてこなかった貴様らに、与えるとはどういうことなのか、本物の魔法を教えてやろう」
* * * * *
「……というわけで、三人の王子さまは魔女に呪いをかけられて猫の姿になったのです」
パタンと白紙の本は閉じられる。
少女はふと窓の外に深く垂れこめる下弦の月をみて、それから丸まるように寝息をたてる三匹の黒猫たちをみて、クスリと笑みを浮かべた。すやすやと眠っている黒猫たちはきっと気づかないだろう。自分たちがかつては魔法の国の王子であったこと。好き勝手に世界を滅ぼし、玉座だけに執着した愚かな兄弟喧嘩の幕は誰がおろしたか、など。
所詮は夢の中の物語。
「この続きは、また明日」
繰り返し語られるのは、魔法の国でおこった永遠のおとぎ話。
青い瞳も赤い瞳も黄金の瞳も、今はただ静かに眠っている。
「おやすみ、愛しの王子様」
ボーンとひとつ。真夜中の時計が誰もいない古城の奥で静かに響いた。 (完)

プロムナードとは
遊歩・散歩を意味するプロムナード。「日常の中にほんの少しの非日常を」というコンセプトを元に、短く仕上げた物語たちのこと。皐月うしこオリジナルの短編小説置き場。
※読了時間については、1分あたり約750文字で計算しています。