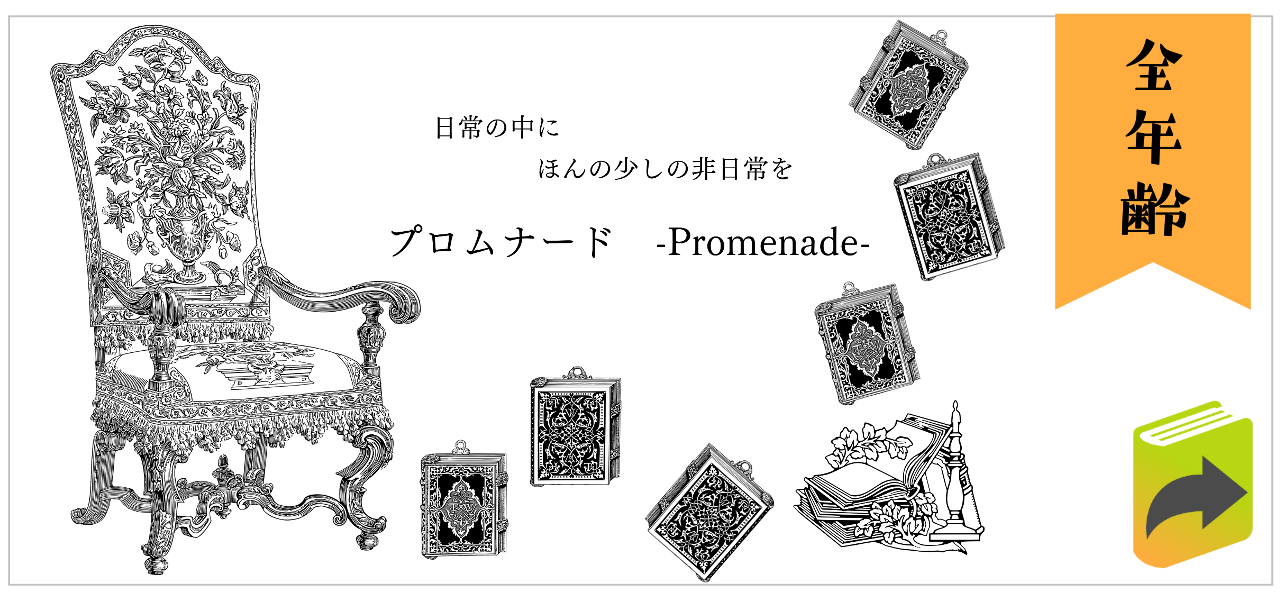読切「無配信アイロニー」
概要
2022年5月に刊行された神無月愛さま主催の「本と笑いアンソロジー『破顔書架』」参加作品となります。
》》寄稿詳細はこちら
無配信アイロニー
読み:むはいしんあいろにー
公開日:2022/05/某日
ジャンル:現代・恋愛
文字数:約7000字
読了時間:約10分
タグ:失恋/ハッピーエンド/友情/恋人
本編「無配信アイロニー」
「信じらんない」
頭からかぶった冷水が前髪を伝ってテーブルに落ちていく。ぽたぽたと擬音付きに感じるのは、降り始めた雨粒に似てわずかな水飛沫をあげているせいだろう。
実際、午後二時半の繁忙時間。賑わう店内の窓の外では雨が降り始めたのか、また一組のカップルが肩を濡らしながら来店を告げている。だがしかし異常な静けさに包まれた店内の様子にそれまでの愛想を消し、場違いな空気に息をのんだのがわかった。
嗚呼、可哀想に。
あなたたちは何も悪くないと教えてあげたい。
カップルだけではなく、店内にいる全員に申し訳ない気持ちがこみあげてくる。
この場合「場違い」なのは来店したばかりの若い恋人たちではない。もちろん店員でも、その他の客でもない。原因はカフェ・モンステラの右奥に設けられた二人掛けの席にある。
一方を壁と同化したソファー席、もう片方は細い四つ足の四角い椅子。その椅子がけたたましい音を立てて倒れると同時に、冒頭の言葉を店内に響く声量で騒ぎ立てた女は直後、目の前の男に向かってグラスの中の水を吹っ掛けた。
「どうして、わかってくれないの!?」
目の前の彼女のヒステリーよりも一瞬にして静まった店内の方が気になると言えば、また彼女は感情のままに叫ぶだろうか。
半分泣いたような顔をしているが、泣きたいのはむしろこちらだと肩から息を吐き出す。そんなことを思ってしまうからきっと、彼女は怒って叫ぶ羽目になったに違いない。
「……樹里(じゅり)ちゃん」
顔をあげずに前髪から滴る水を見つめて呟いたはずなのに、なぜか目の前の彼女=樹里がビクリと強張ったことを真人は知った。
「とりあえず、座ろっか?」
人当りの良い微笑みを浮かべて優しい声を意識する。なだめて、あやして、時間をかければ、今までの女のように麻生樹里もまた、憤慨しながらもやがて落ち着きを取り戻すはずだった。
「……っ、もう知らない。サヨナラ」
自分のカバンを持って店内を飛び出した樹里が、雨が降る窓の向こうを走っていくのが見えた。自然と顔をあげた視界は、必然的に集まる視線達とかち合う。
「あ、すみません」
まだ水滴をまとった髪のまま謝罪を口にすれば、人々は驚きをかき消すように動き始める。その証拠に店員が「だいじょうぶですか?」とおしぼりを提供してくれたので、立花真人はお礼を言ってそれを快く受け取った。
濡れた髪を拭いて、濡れたテーブルを拭いている間に店員が倒れた椅子を起こしてくれていたので、またお礼を付け加えると気まずそうに「これ」と薄茶色の表紙に虹色の箔押しがされた本を手渡される。樹里が落としていった本らしいそれを受け取って、それから一人。真人はソファー席に背中をあずけて息を吐く。
得意じゃない冷めたブラックコーヒーがさらに気分を沈ませる。
「……はぁ」
窓に映る顔は愛想のいい微笑みを消した無表情の能面。
それなりに「映える造形」をしているらしく、時代に受け入れられた容姿のおかげか否か、投稿する自分の顔だけでそれなりに稼げるのは有り難い。そうしてまた有名になった代償としてよくモテた。
事務所に所属するほどではない一般人のラインにいるのに、知る人ぞ知るカテゴリーに属するせいで、今日の事件はハッキリ言って憂鬱になるほど自己嫌悪に見舞われた。
「めんどくさ」
誰にでもなく一人呟いて真人は窓からテーブルに顔を戻す。と同時に小刻みに震えた携帯の画面を覗き込んでみれば、案の定「まなぺ、水も滴るいい男って?」とwの羅列とともに相方からメッセージが届いている。
早すぎる情報社会に頭が痛い。
想像しなくても、今頃樹里がSNSで「別れた」と拡散している場面が浮かんだ。
「笑い事じゃねぇし」
「何人目だよww女遊びもほどほどにしねぇと炎上すんぞww」
「知らねぇよ」
「で、今度は何で怒らしたわけ?」
そう問いかけられて思考を辿る。樹里は確か「信じらんない、どうしてわかってくれないの」と言っていた。
樹里と付き合い始めたのは一か月前だった記憶がある。SNSのDMで会話を繰り返すうちに意気投合という流れで始まったのだが、思えば彼女は「まなぺ」という存在が好きだったのだろう。
イベント大好きイケメンで、朗らかで面白く、ファンにも優しく、仲間思い。
キャッチコピーにしては長いそれが、真人を表現するネット上の言葉。けれど現実として生きた人間にそれを二十四時間三百六十五日当てはめるのは難しい。
真人だってしんどいときもあれば、疲れたと感じる日もある。癒されたいと一人になりたいときもある。というより、むしろそちらの方が「素」といえばいいのか。ともかく今日、樹里が言うには「一か月記念日」とやらを失念していた真人は寝坊した挙句、プレゼントのひとつも用意してないばかりか「え、今日って何か特別な日だっけ?」とデートの理由を尋ねる失態を侵した。
「記念日ってそんなに大事なもん?」
ぺらぺらと樹里が落としていった茶色の本の頁をめくる。最近映画化された話題の小説らしい内容が目に入って、そういえば映画を見たいとか言っていたなと記憶の断片を掘り起こされた気がして、頭痛が悪化した。
「女はそういうの好きだよな。特にまなぺのイメージはそういうの大事にしそうだから余計じゃね?」
「……だる」
「そういうなってwwてか、そういう本性がなんで付き合う前にバレねんだよ」
「俺が知りてぇわ」
付き合う前も後も自分の態度は変わらない。「寝てた」「ごめん」「配信準備してた」「ごめん」「撮影で忙しい」「ごめん」おおよそ、交わす会話は変わらないはずなのに、付き合う前にも「俺たぶんずっとこんなんだよ?」と確認をとっているのに、どういうわけか。彼氏と彼女になると求められるものが変化するらしい。
「樹里ちゃんのことは割と本気で好きだっただろ?」
「どうだろ」
「またまた、付き合えた日のテンションは記録にばっちり残ってるんだよな」
「俺もう配信やめよっかな」
「そういうのは、それを出来ない奴が言う台詞」
「だって配信、楽しいし」
そこまでメッセージでやりとりして、真人は店内に意識を向け直す。
すでに先ほどの事件を知っている幾人かは店をあとにして、順番待ちの客が隣の席につくころだった。
冷めきったブラックコーヒーを一気に飲み干す。
「……苦」
思わず顔をしかめて舌を出してみれば、席に着いたばかりの隣の客と目が合った。くすりと笑われたのは少し恥ずかしい。
もう二十代も半ばに差し掛かる大人にもなって味覚が幼稚なのはコンプレックス。照れ隠しに愛想笑いを返してみれば、一瞬驚いた若い女性はすぐに頬を染めて明後日の方を向いた。
これもいつものこと。
雨の降る店の外に出るのは億劫だが、ずっとひとり寂しく居座っているわけにもいかないので本を片手に席を立つ。そのとき見知った顔が窓を叩いて自分の名前を呼ぶのを聞いた。
「……情報社会、まじ怖」
呟いてから曖昧な顔で店の出入り口を指さすと、先ほどメッセージのやり取りをしていた相方は親指と人差し指で丸を作り、笑顔で二回ほどうなずく。
「なんで迎えに来てんだよ」
「傷心のまなぺの顔を一番に拝んでやろうと思って?」
「それはどーも」
携帯のカメラが記録するのはご愛嬌。おおかたテロップで「傷心のまなぺ発見」「不機嫌オーラ全開」「迎えに来てあげたオレ優しい」と装飾するつもりだろう。このご時世、ネタになればなんでもいい。自分で選んだ道なのだからそれでいい。
いつか見向きもされなくなる日が来るだろう。世界は目まぐるしく移り変わり、時代は栄光を置き去りにして流れていく。
「手に何持ってんの?」
センチメンタルな気分を隠して「小説?」と首をかしげた。
「まなぺ、小説とか読むキャラじゃねぇだろ」
「笑うなよ。あー、もー、久しぶりにメンタルやられてんだから優しくして?」
「その顔、無駄にイケメンなのがむかつく」
笑ってくれる存在はありがたい。
落ちた気分が浮上していくのを感じる。それとも向けられたカメラの存在が、そういう気持ちにさせてくれるのかもしれなかった。
「はい、撮影終了」
「おつかれー」
編集用の尺を十分にとってからカメラを切った相方の言葉で表情が消える。漫画で言う「すん」という効果音が妥当なのかもしれないが、その顔は「まなぺ」には似合わない。
「さて、どうする?」
「にーやん家は?」
「オレんち、別にいいけど。何もねーよ?」
「それかこのまま映画観に行く?」
「いいね、いいね。まなぺ、ちょうど小説持ってんだし、映画化されたとかいう話題のそれ見ようぜ」
「絶対配信用じゃん、鬼かよ」
「仕事してる方が気も紛れるって。さとっちと、かなるんも呼んでさ」
「来るかな?」
「こんな面白い日にあいつらが来ないことはない」
言いながら携帯片手に連絡している。相変わらずフットワークが軽いなと嘆息しながら真人も携帯の画面に目を落とした。
配信は四人グループ。まなぺ、にーやん、さとっち、かなるん。高校時代に仲が良かったメンバーだが、それぞれ地元を離れて一度大学や専門学校にばらけたのち、同窓会で再会して今に至る。再会の感動に浮かれて配信してみた動画が思いのほか好感触だったうえに、連続してバズった幸運が重なり、思い切ってそれを仕事にしたのがそもそもの始まり。
二十代半ばの男たちによる何気ない日常。
登録者数も再生回数もおかげさまで安定している。
「……どこで生き方間違えたんだろ」
「ちょ、まなぺ。そういう面白い発言はカメラ回ってるときにしてよ」
「にーやんは、いつも楽しそうでいいな。悩みとかないだろ」
「オレは今が最高に楽しいから」
「男二人で相合傘して歩いてんのに?」
「あとでさとっちか、かなるんに撮ってもらおう」
「なんでも配信につなげるのやめれ」
「視点や観点を変えるだけで世界はもっと楽しくなる。こういう何気ない日々だって、いつか懐かしむ日が来るかもしれねぇだろ」
大袈裟ではなく大真面目で語るにーやんの瞳は、いつもキラキラと輝いている。「いつも」というのは語弊がある。再会した当時、にーやんは腐った魚のような目をしていた。なんでも社会のつまらなさに辟易していたそうで、にーやんが言うには「動画制作は天職」らしい。企画し、編集し、配信する。
「永遠に映画の監督やってる気分」
そういって笑う顔に嘘はない。心から楽しんでいるのがよくわかる。
「あ、さとっち達、来た」
手を振って呼びかける方へ体を向けてみれば、確かにそれらしき二人組が手を振り返している。透明の傘を差した全身カラフルな原色男子が、さとっち。対照的に真っ黒な傘を差しながら全身真っ黒な服をきてフードをかぶったのが、かなるん。
「まなぺぇぇぇえ、独り身おめでとー」
「うわ。さとっち、抱き着くなって。めでたくねぇし」
「はい、これあげる」
「え、かなるん、なにくれ…ッ!?」
手の平に乗せられた物体を確認するなり悲鳴を飲み込んで固まった真人に、合流した二人組は爆笑し、にーやんは嬉々として撮影している。
雨に濡れた地面に放り投げられたのはミミズの玩具。
にーやんがアップでそれをカメラに映しているが、一瞬本物と見間違えた真人はそれどころではない。
「あー、まじ心臓痛ぇ」
「なに、失恋がそんなにこたえてる?」
「さとっち、違ぇから。かなるんもそういうイタズラやめてね」
言えばかなるんは謎のポーズで拒否を示す。一番背が低くて可愛い容姿をしているのに、全身黒いうえに、目深にフードをかぶっているからその良さはいまいち発揮されていない。
にーやんに言わせれば「ギャップ萌え」らしく、キャラづくりは欠かせない要素だなんだと力説されかねないので黙っておくことにした。
「映画見んだろ。早く行こうぜ」
「だから、押すなって」
進行がさとっちにゆだねられるのは、もう仕方がない。昔からそう。どれだけ抗ってもこの渦には逆らえず、結局は流されるようにして巻き込まれている。
「どんなときでも働いてて俺たち偉い」と、ぐしゃぐしゃと頭を撫でてくる原色が目に痛いのだけは勘弁してほしいところだが。
「……あ」
映画館が目前に差し迫るころ、かなるんが立ち止まって携帯画面を覗き込んだ。
一体どうしたのかと全員でそれを眺めてみれば「……ぽえぽえ」と小さな声で呟くのが聞こえてしまって地味につらい。残念なことに、それが何を意味するのか瞬時にわかってしまう間柄なのはこの際脇に追いやっておこう。
「よーし、映画はかなるんお勧めのそれにしよう」
「待て、にーやん。今日は俺をなぐさめる会なんだろ?」
「その堅苦しい小説よりも幼女アニメを男四人で見る。面白い方をオレは撮るね」
「賛成。ぽえぽえで行こう」
「……まじかよ」
本当にチケットを四人分購入してきたにーやんのせいで、幼女が憧れるキャラクター等身大と並んで撮影し、親子連れが視聴しない時間帯なのか妙に空席が目立つ館内に着席し、真人は自分の意向とは違う映画を見る羽目になっていた。
「はぁ……ま、いっか」
結局、今日はどっちにしても気分は低迷したままだっただろう。
一方的に振られたとはいえ、真人なりに好きだったのは嘘ではない。引き留めることも、追いかけることもないほどには薄い恋心だったが、芽生える前に枯れた花にもそれなりに愛着はある。
柔らかな声が好きだった。ふとした表情が可愛いと思っていた。実は小説を読むという趣味を「似合わない」と笑わずに受け入れてくれたばかりか、お勧めの本を共有しあえる共通の趣味は舞い上がるほど嬉しかった。樹里が落とした茶色の本。貸してくれるつもりで今日、持ってきてくれたのだろう。映画は樹里とみたかった。
告白してきたのは樹里で、振ってきたのも樹里だったが、本当は自分から告白しようと思っていたほどには好きだった。小刻みの記念日は祝わなくても、一緒にいられる日々を仲間内に惚気てしまうくらいには好きだった。
一か月という短い期間のはずなのに、何年も付き合っていると錯覚するくらいには居心地が良かった。出来れば、何年も付き合っていきたかった。
「……っ」
最後尾に男四人で腰かけて、館内の照明が落とされて、流れ始めた予告や広告を眺めているとふと頬に何か流れるのがわかった。
雨の当たらない室内なのに、前髪から滴っていた水は乾いたはずなのに、ぽたぽたと擬音付きに思えるほどの雫が頬を濡らしていく。
「来てくれて、ありがと」
小さな声は、聞こえてほしい人たちには多分届いたことだろう。
この映画が終われば、また照明がついて外に出るころには、たぶん笑えるようになっている。不覚にも、幼女アニメだと内心馬鹿にした映画が胸に刺さり、感動してしまったのを涙のネタに変えて、たぶん未来は笑えているだろう。
それでいい。今はそれで。
映画が終わり、映画館を出た先で走り去っていったはずの樹里の姿を見つけて衝撃に足を止めることになったとしても。その背後で顔を見合わせて「やれやれ」という表情をしている仲間たちが仕組んだ罠に気付いたとしても。
「泣いてくれるくらいには、好きでいてくれたんだ」
「……樹里ちゃん」
恐る恐る近づいて、見上げてくる顔を見下ろす。
雨はすっかりあがって、水たまりに煌めく夕焼けに沈んだ町が街灯をつけ始めているが、その目が同じくらい赤いことを知って胸がぎしりと痛んだ。
「本、落としたことに気づいて、お店の人に聞いたの」
「これ?」
小さくうなずく顔がすぐそこにある。繋ぎとめているのは茶色の本だけ。渡してしまえばそれで終わり。その未来が無性に嫌で、イヤでたまらなくなった。
「ごめん、樹里ちゃん。別れるの、なしにしてくれないかな」
声が震えて聞こえないといい。
カメラが回っていなくても、もう一度会えた瞬間の感情を大事に残しておきたいと思った。
「私もごめんね。一人で舞い上がって、浮かれちゃってた。自分だけが好きなのかもなんて不安になって……八つ当たりにしても、水をかけるのはさすがになかった。本当ごめんなさい」
ぺこりと頭を下げている目の前の存在に、急に愛しさがこみあげてくる。
あの時は確かに苛立ちを感じていたはずなのに、それさえ全部忘れてしまえるくらいには好きだなんて、今さらながら実感する。
「樹里ちゃんさえよければ、一か月記念日、やり直しさせてほしいんだけど」
「あ…えっと、あの…本当はね、一か月記念日なんていいの。真人くんが全然会いたいとか好きとか言ってくれないから、確認したかったというか…今日一日、一緒にいるための口実にしたかった…というか…その本も。でも、まだ一緒にいてくれるなら、その…おねがい、します」
パッとあがった顔が花開いて、恥じらう姿に内心悶える。
直視できなくて顔をそむけてしまったが、手で口元を抑えないと冷静を保っていられないほどにはにやけてしまう。
「世話がやけるなぁ」
「うわっ、ちょ。撮んなって」
「これは配信用じゃなくて、いつか結婚式で使うかもしれない用」
「なっ!?」
「じゃーね、樹里ちゃん。真人のこと後はよろしく」
そう言って三人揃って消えていく仲間の背中が頼もしい。自分がいかに恵まれているかを噛み締めながら雨あがりの空気を肺に吸い込んだ。
「とりあえず、映画でもどうですか?」
「はい、よろこんで」
差し出した本に、指が重なる喜びをカメラではない瞳が映している。自分でも確かめようのない顔を見せているのはただ一人。照れくさくて、気恥ずかしい。それでも隠せない想いを伝えられるなら、虹色の箔押しが揺らめく視界に心からの笑顔を。
(完)
あとがき
笑顔をテーマにした物語が私にとっては難しすぎて、色々と書き直してようやく落ち着いた作品がこちらになります。ファンタジーで書くはずが、現代恋愛ベースになってしまいました。配信を仕事にするって現代ならではって感じ。そしてあろうことか、最初に書き上げた時に本を登場させるという一番大事な描写を失念していた、なんて笑えない失態も・・・最終的に全要素詰め込めたので結果オーライです。
普段はこういう作品を書かないのでドキドキしています。
アンソロジーだからこそ生まれた世界を楽しんでいただけたらいいな。
皮肉の意味で用いられるタイトルの「アイロニー」は表面的な立ち振る舞いによって本音を隠すことという意味があり、今回はそちらの含みを持たせる形にしてみました。本当はめっちゃ好きなのに、なんかカッコつけるのが日常化している配信男子。苦手なブラックコーヒーを飲んでみたり、小説を読むことを隠してみたり、目が合った若い女の子に微笑んでみたり、だけど本命の彼女には愛想のない態度をしちゃう不器用な彼。
彼女目線の物語ではたぶん、もっと違う一面が出てくるんだろうと思います。
「無配信」の一片を見てしまったら、どんどん気になってしまうのは人間の性ですかね。
では、あとがきはこの辺で。

プロムナードとは
遊歩・散歩を意味するプロムナード。「日常の中にほんの少しの非日常を」というコンセプトを元に、短く仕上げた物語たちのこと。皐月うしこオリジナルの短編小説置き場。
※文字数については各投稿サイトごとに異なる場合があります。
※読了時間については、1分あたり約750文字で計算しています。