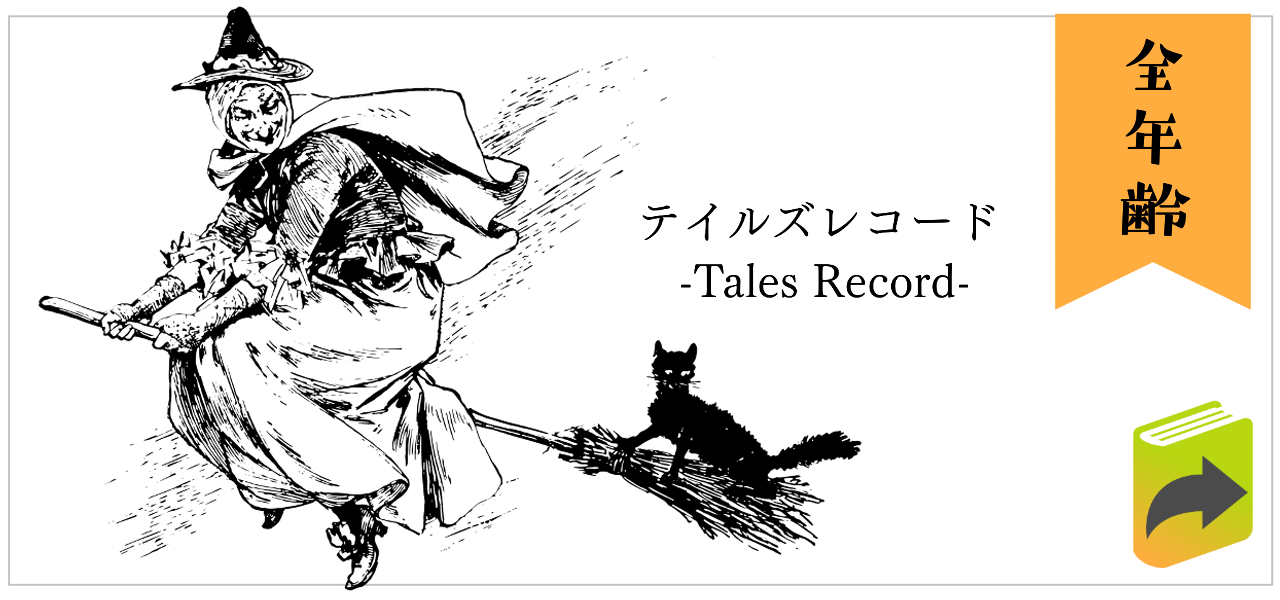紫水晶が眠る呪いの谷で(ありふれた魔女たちの日常より)
この作品は、2018年9月発行「ありふれた魔女たちの日常」に収録されました。
その他注意事項は必読を確認ください。
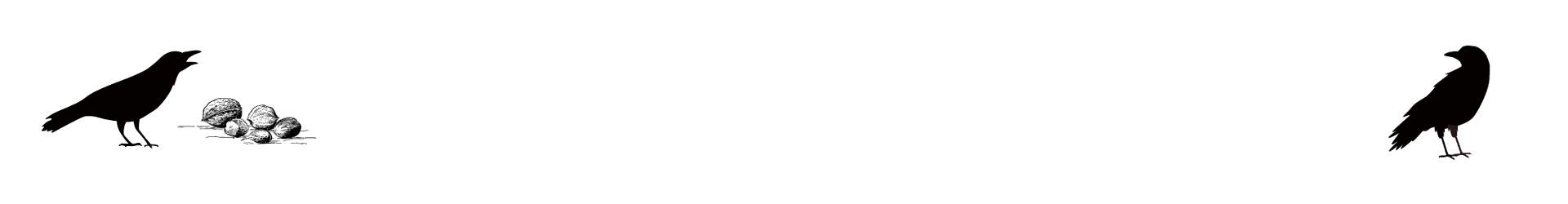
ありふれた魔女たちの日常
紫水晶が眠る呪いの谷で
呪い。
それは魔女自身にも起こりうる悲劇だということを忘れてはならない。
魔女の世界で有名な詩人ポエトリー・マリエンサーが残した言葉は、枯れた大地に切り込みをいれたような深い谷底に住む女を表現するのにピッタリの言葉だった。
彼女の名前をリリーナ。
白い肌に長い白髪が美しく、四十年前の彼女の二つ名は「谷の精霊」だということを忘れてはならない。
「おはよう、イリアス」
鈴の音が響くような声が、今日も決まった時刻に谷底から聞こえてくる。
リリーナの白い髪が紫色に染まるほどの石群の中、少し物憂げにかげった彼女の顔にイリアスと呼ばれた青年の姿が映り込む。黒い髪に黒い瞳。リリーナと正反対の容姿を持つ青年は、悲壮な表情のまま口を開けて固まっていた。
「気分はどう?」
イリアスは何も答えない。
いや、答えられるはずもなかった。
リリーナは紫水晶に閉じ込められた青年を見て、一人悲しそうに瞳をふせる。手を伸ばして触れたその表面は、冷たく滑らかな質感をそっと伝えていた。
「あなたが石になって、今日でちょうど四十年目よ」
口を開けたまま紫水晶の中で永年の時を過ごす青年の黒い瞳を覗き込むように、リリーナはまた小さくつぶやいた。
話しかけても答えてもらえない日々を繰り返すこと四十年。
毎日毎日足を運ぶ生活も思い返せば短く、実に長く気の遠くなるような月日だった。
「私はすっかりおばさんになってしまったのに、あなたはずっと若いままでいいわね」
皮肉めいた言葉にも答える声はどこにもない。
紫水晶を覗き込む白髪の女の顔には、重ねた年齢の数だけ生きた証が刻まれていた。
「シワも随分と目立つようになったでしょう」
冷たく滑らかな水晶の表面と違い、リリーナの顔は乾燥した谷の感触を指先に訴える。白い髪は生まれつきもつものだが、今では若いころ以上に自分の容姿に馴染んでいるとさえ思えるほど。
そして、リリーナにはもう一つ。生まれつき持っているものがあった。
「こんな姿になっても、私を愛してくれるのはあなたくらいよ」
それは、呪い。
生まれた時にかけられた呪いは、自分を愛してくれる人にだけ効力を発揮する悲しい魔法。
「自分を愛してくれる人が紫水晶に閉じ込められる呪いの意味を知っているのかしら」
リリーナは手のかかる子どものようにイリアスに向かって微笑みかける。
「水晶に閉じ込められたままの姿でいても、あなたに私の声は聞こえているし、もう四十年だもの。いい加減、知っているはずよ」
そう問いかけられてもイリアスは表情一つ変えようとはしなかった。
その黒い瞳を覗き込めば、いつも飄々(ひょうひょう)としてふざけたことを言っていた人物と同一とは思えない。村から谷へ、谷を守る宿命を背負った魔女への貢物として、物資を運ぶ役目を担った青年。それがイリアスだった。枯れた大地に住む魔女を心配して、荷物とは別に、毎日運んでくれた白い花が記憶の中で真新しい。
けれど、もう四十年。
イリアスが来る日を心待ちにしていたリリーナが、それを恋だと認識し、またイリアスもその感情が特別なものであると伝えたあの日。二人重ね合った唇が離れる瞬間に、イリアスは紫水晶に飲み込まれてしまった。
「私への愛が消えれば、いつでもその水晶の中から出てこれるのに」
それは望んでいるようで望んでいない言葉に違いない。
紫水晶に閉じ込められている限り、リリーナはイリアスの愛を感じ続けることができるのだから。
「イリアス、愛しているわ」
そうしてリリーナは、物言わぬ石にその唇を重ね合わせる。
四十年前のあの日よりもいっそう深くなった気持ちをのせて、魔女は永遠に愛する人を眺めながら孤独の日々を過ごすのだ。呪いがとけるその日まで。
(完)
Tales Recordとは
皐月うしこの童話みたいな短編置き場。「今日もこの世界のどこかで生きている」をキャッチコピーに綴ります。なさそうであり、ありそうでない。そんな狭間の物語です。