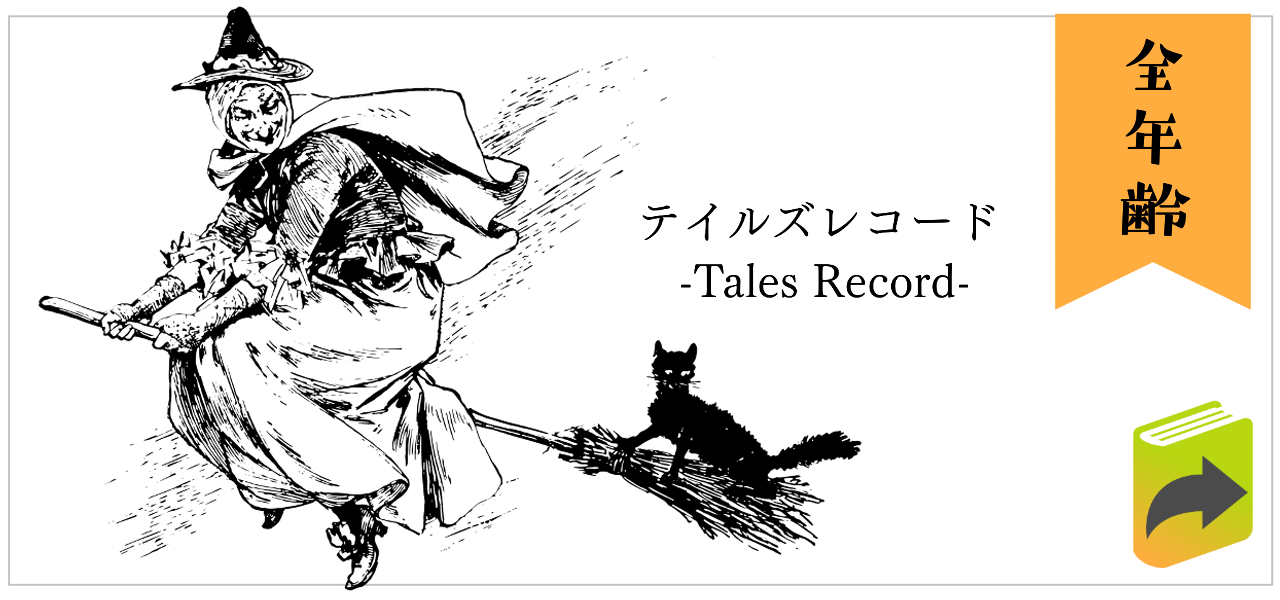魔女が知らない白猫の秘密(ありふれた魔女たちの日常より)
この作品は、2022年5月発行「ありふれた魔女たちの日常」に収録されました。
その他注意事項は必読を確認ください。
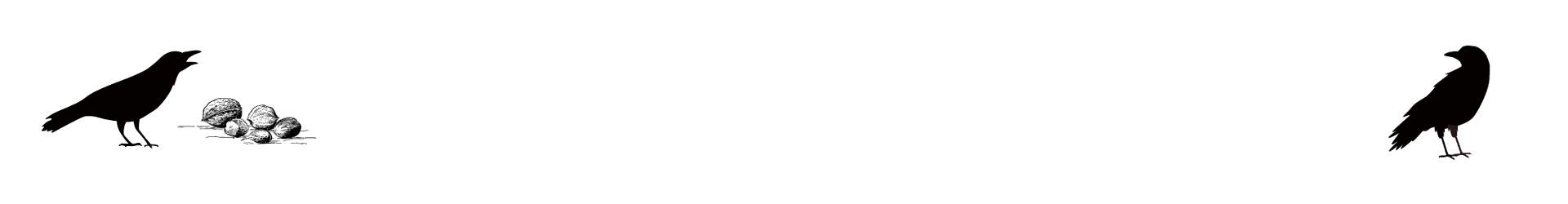
ありふれた魔女たちの日常
魔女が知らない白猫の秘密
アルデンテ通り三丁目に住む老婆エルモンテは、どうやら魔女らしい。らしいというのは、同じ町に暮らす住民たちの噂に過ぎない。年老いた女が、たったひとりで、町の一番端にある日当たりの悪い家に住んでいるせいもあるだろう。
壁に飾られた写真を見る限りでは、昔はそれなりに美しかったのかもしれないが、今は見る影もない。曲がった背中はもちろん、手や首のしわやシミは、エルモンテが老婆であることを物語っている。しかし、身体に不自由のない老婆なのだろう。
伸びた白髪をひとつに結び、色褪せた服を着て、時折一人で買い物に出かけている。会話もできる。したいかどうかは別にして、と住民は続ける。エルモンテは、結婚もせず、子どももいない。なんでも、教師をしていた両親が厳しく、幼少期から家の中で勉強ばかりしてきたらしい。博識だが、世間知らずな変わり者。オシャレな靴や髪飾りよりも、本やペンを喜ぶ少女だったという。その頃は、今よりもっと小さな町だったせいか、エルモンテと年が近い子どもは少なかった。そうして、友達も、知り合いもいないまま、年頃の娘になったころ、不運にも両親が事故で死んだ。
親戚もいない哀れな娘。幸運なことに、財産と家は残ったが、エルモンテは社会に馴染めず、ますます引きこもった。当初、年頃にありがちな出会いの流れで、町で彼女に声をかけるものはいたらしい。それでも、家に招かれたものは早々にして退散したという。
何度か続けば、次第にエルモンテに声をかけるものはいなくなった。年月だけが流れ、エルモンテと親しくなったものはおらず、ましてや歯が浮くような色恋話もない。かつて交流を持った人物たちも町を去り、老いて死に、過去のエルモンテを語るのは噂だけ。
小さな町で、エルモンテは悪い意味で有名になりすぎた。そのせいとは言わないが、婚期を逃し、不自由なく暮らし、結果、エルモンテはひとりの老後を過ごしている。
そんなエルモンテも、生きていればそれなりに顔なじみがあるというもの。けれど、それも束の間の出来事だった。
エルモンテの三軒先に住む、若い夫婦の話によれば、二年前のある夜、気を利かせた奥さんが「作り過ぎたから」と、シチューを持っていったらしい。その日、家の中で老婆エルモンテは火にくべた黒い鍋をかき混ぜていたという。ただ、鍋をかき混ぜていただけなら問題はない。夕食時だ。どこの家でもそうであるように、エルモンテも夕食の準備をしていたのだろうと納得できた。
ところが、シチューを運んだ三軒先の若い奥さんは違った。
訪れたエルモンテの家の中には、表現しがたいほど苦い煙が立ち込めていて、エルモンテがかき混ぜる毒色の鍋からは、お世辞にも人が食べるものだとは思えない臭気が満ちていたという。しかも、当の老婆エルモンテは、不気味な笑みを浮かべながら鍋から顔をあげ、訪ねてくれた奥さんに向かって「白い毛の生えた青い花は見かけたか?」という変な質問をした。
「い、いいえ。そんな花は、どこにも見かけないわね」
「ほんの少しでいいんだがな」
「エルモンテ、青い花なんて何に使うの?」
「そりゃ、お前さん。切り刻んで、ぐつぐつ煮込むのさ」
そのとき振り返ったエルモンテの顔は、身の毛もよだつほどだったというのだから、シチューを無理矢理玄関の、それも足元において、三軒先の奥さんは逃げ帰ったという。そしてそのまま、命からがら息を切らせた彼女は、「エルモンテは魔女に間違いないわ」と、家の中で呑気に欠伸をこぼしていた夫に向かって告げたらしい。
「どうせお前の勘違いだろう。いくら不気味だからって、相手は一人暮らしのばあさんだ」
「そうはいっても、あなた。白い毛の生えた青い花なんて、見たことがある?」
「俺はないな」
「私だってないわよ。それを切り刻んで、ぐつぐつ煮込むんですって。あの不気味な笑顔、ああ、恐ろしい。きっと人殺しの毒でも作っているんだわ」
「そうはいっても、無いものを煮込むのは難しいさ。考え過ぎだ。からかわれたんだよ」
「いいえ、あなた。エルモンテは絶対に魔女だわ」
かたくなに意見を曲げない妻に、それまで傍観を決め込んでいた男も興味が湧いたのだろう。翌日、妻の作ったシチューの鍋を口実にして、男はエルモンテの家を訪れていた。
「おーい、ばあさん。昨晩は、うちのやつがシチューを置いて行っただろう。鍋を回収しにきたんだ、開けてくれ」
「ちょいと待っておくれ。今は手が離せない」
男は、中から聞こえてきたエルモンテの指示に従って、しばらくエルモンテの家の扉の前で待っていた。数分、待たされていた身からすれば、体感はそれ以上だったのかもしれない。正確には十二分四十五秒後、エルモンテの家の扉が開いた。
「あんたんとこの嫁は、料理がうまい。大事にするんだね」
「そりゃどう……は、なんだ、その恰好」
「なに、酷く暴れられたんで、ちょいとばかし手こずっただけさ」
「ばあさん、全身、それは血じゃねぇか?」
「そうだよ。運よく、白い毛の生えた青い花が手に入ってね」
「じゃあ、まさか。それを使って」
「ああ、もう大人しくなったから心配はいらない。さあ、鍋を持って、さっさと帰っとくれ。わたしゃ、これから、ちぃっとばかし忙しい」
一瞬の出来事。そう思ったのは、玄関先で取り残された男だけだったに違いない。
今見たもの、聞いたことは夢だったのか。あまりに衝撃過ぎて、現実逃避をしかけた脳は、たしかに来るときには持っていなかった鍋の重さを思い出して、先日の妻同様、一目散に逃げ帰った。
「あなた、どうだった?」
「お前、あの家には二度と近づくな」
「え、なに。どういうこと?」
「エルモンテは魔女だ。お前のいうとおり、人を殺したのかもしれない」
「そんな。どうしましょう」
「いいか、変に騒がず大人しくしていよう。もしもエルモンテが訪ねてくるようなことがあったら、いない振りをしてやり過ごすんだ」
小さな町は、隣家から隣家へ噂が回る。夫婦は生まれ育った町で、その他大勢がそうであるように、平穏無事に暮らしていくことを望んでいた。だからこそ、これ以上、犠牲者が出ないことを祈り、エルモンテを刺激しないことを誓いあい、エルモンテが魔女であることを周知の事実として受け入れたのだった。
それから二年、町は平穏無事に日々を過ごしている。
エルモンテは相変わらず不審がられているが、特に問題は起こっていない。誰かが失踪したという話もなければ、殺されたという話もない。アルデンテ通り三丁目には、今日も平和な時間が流れている。
若い夫婦に子どもが生まれ、赤子の泣き声が夜通し聞こえたときも、エルモンテは何もしてこなかった。夫婦はもちろん、町中が警戒していたが、取り越し苦労だったと、胸をなでおろした日が懐かしい。そう言って、笑えるほどには平和だった。
「あら、見かけない猫だわ」
子どもが眠った昼下がり。子守歌代わりに昔話を聞かせていた女は、少しお茶にしようと顔をあげた先で、視界に入った窓の向こうに猫を見つけた。猫は、子どもに語っていた話を一緒に聞いていたに違いない。真っ白な毛を揺らし、優雅に腰をあげて立ち去る姿に、そうだとわかる。一目で見惚れるほど美しい白猫は、何も言わずに、軽快な足取りで窓の向こうに消えた。
どこへ行くというのだろう。
そのあまりの美しさに思わず窓まで駆け寄って、女は猫の行方を目で追いかける。すると、どうだろう。エルモンテの家へ脇目も振らずに向かっていくではないか。猫に言葉が通じるのかはわからないが、女は慌てて窓を開けると、猫に向かって「そこは魔女の家よ」と伝えた。
白い猫が足を止めて振り返る。空を閉じ込めた宝石のように青い瞳が揺らめいて、可愛らしく「にゃー」と鳴くと、当たり前のようにエルモンテの家の中に入っていった。
「おや、ハント。今日は珍しく早いじゃないか」
今しがた家の中へ入ってきた猫に向かって声をかけたのは、この家に暮らす老婆しかいない。火にかけたヤカンから湯気が出ているのは、ちょうどお茶でも飲もうとしていたのだろう。テーブルの上にコップがひとつ置いてある。
「お前さんも飲むかい?」
エルモンテの問いかけに、ハントと呼ばれた白い猫はため息をひとつついて、「いいや」と答えた。
「そうかい、なら、わたしの分だけ入れるとしよう」
コップに熱いお湯が注がれていく。その音だけが室内に染みわたり、静寂が老婆と猫を包んでいた。立ち上る湯気は、か細く、白い。香ばしい匂いにホッと息つくのかと思いきや、老婆エルモンテと白猫ハントは同時に顔をしかめて「げほ、ごほ」と、むせた肺の反撃に従った。
「相変わらずひどい匂いだな、エルモンテ。いい加減、お茶のひとつくらい、まともに入れたらどうだ?」
「いいんだよ、わたしゃ長年、これを飲んできたんだ」
「まったく、壊滅的に料理が下手なだけじゃなく、お茶もこれじゃ、先が思いやられるぜ」
「熱いお茶もまともに飲めない猫に言われたかないよ」
「ああいえばこういう、そんなだから魔女なんて呼ばれるんだ」
白い猫はその美しい瞳を歪めてテーブルの上に飛び乗ってくる。鼻先をしかめるほど酷い臭いなのか、けれど、エルモンテは構わずに得体のしれないお茶を一口、ずずっと音を立てて飲み込んだ。
「魔女なんてのは、町の連中が勝手にそう思ってるだけさ」
「そう思わせるだけの要素はたっぷりあるけどな」
「なんだい、今日は随分と突っかかってくるじゃないか」
エルモンテは、からかうつもりで笑いを浮かべただけだろう。それでも見た人が不気味だと思うくらいには、恐ろしい笑顔を浮かべたために、ハントの白い毛が一瞬ぞわりと膨れ上がった。
「だから、その笑顔をやめろって」
「生まれた時からこの笑顔で生きてんだよ」
ふんっと鼻を鳴らしたエルモンテの仕草に、白猫は一息ついて、膨れた尻尾をなだめるように毛づくろいを始める。
猫のハントは老婆エルモンテが、二年前の雨の日に拾った猫だった。
ずぶ濡れ以上にボロボロの出で立ちで、生きているのか、死んでいるのか、よくわからないほど酷い有様だった。馬車にでも轢かれたのか、野犬にでも襲われたのか、詳細はわからないが、エルモンテが見つけた時には全身傷だらけの血だらけで、どうにもならない状態だった。
出来る限りのことをしようと、エルモンテは傷口に効くという薬を煎じ、嫌がるハントを羽交い絞めにして薬を飲ませ、そして十日間に渡る献身的な看病の末、ハントは一命をとりとめた。ちょうどそのとき、三軒先の若い夫婦が訪ねてきたが、当のエルモンテは拾った猫の安否が気がかりで覚えていない。
そのうえ、助けた猫が「俺は、ハント。魔法でこんな姿に変えられたが、本来は人間だ」と喋りだしたために、それどころではなかったというのもある。
「それで、お前さんの魔法をとく方法は見つかったのかね?」
「変身の呪いを解くための魔法ってのは、古来からひとつしかねぇよ」
美しい容姿とは裏腹に、白い猫は口が悪い。毛づくろいが終わらないのか、今度は自分の手の甲を舐めながら、お茶をすするエルモンテの問いにそう答えた。問いかけた方のエルモンテもさして興味がなかったのか「そうかい」と短く答えて、再びお茶をすすっている。
「いや、もっと俺に興味を持てよ」
「こんな年だ。興味なんてもんは、とっくに枯れちまったよ」
「じゃあ、せめて聞けよ。呪いを解く方法が何か、くらい」
「なんだい。真実の愛のキスとでも言うんじゃないだろうね」
「そうだって言ったらどうする?」
「ご愁傷様とでも返すほかないね」
「なんでそうなる」
「考えるまでもないさ。お前さんの声はわたしにしか理解できないんだろ。なぜかわからんが。そんなんじゃ、例え出会えたところで、相手と愛を語りようもない。まあ、相手が猫だっていうなら、それこそ、わたしの枯れた興味が湧くかもしれないね」
「ちっ、話になんねぇ」
「そりゃ、どうも」
のどかな時間。エルモンテとハントのやり取りをよそに、噂好きのアルデンテ通り三丁目は、魔女を慕う白い猫の話で盛り上がっていた。が、しかし、その話の途中で別の話題が降ってきたために、一瞬にして住民たちの関心は入れ替わっていた。
なんでも、どこかの国の若く美しい王子が、行方不明になっているらしい。王様は王子の安否を気にかけていて、見つけたものの願いをなんでも一つ叶えるという。それこそ魔法を使って叶えてくれるというのだから、不死も、不老も、あるいは不治の病も願えばきっと、たちまち叶えてくれるだろう。
みな、血気盛んに、興奮状態でざわめきを広めていく。
嘘か真実か、噂では知りようもない。それこそ、町の片隅で暮らす老婆と白猫の耳には届きようもない。
「はぁ、今日もエルモンテには、伝わらないか。まっ、こんな姿だ。のんびり行くさ」
いつの間に寝落ちたのか。寝息をたてるエルモンテの膝のうえに飛び乗って、その顔をじっと眺めた青い瞳がゆるやかに笑う。そして、眠るエルモンテの頬に、白猫はそっとキスを施した。
エルモンテは気付かない、住民たちも気付かない。
アルデンテ通り三丁目で老婆エルモンテは、人々の噂話を横目に、今日も平和に暮らしている。美しい白猫の呪いが解ける、その日まで。
(完)
Tales Recordとは
皐月うしこの童話みたいな短編置き場。「今日もこの世界のどこかで生きている」をキャッチコピーに綴ります。なさそうであり、ありそうでない。そんな狭間の物語です。