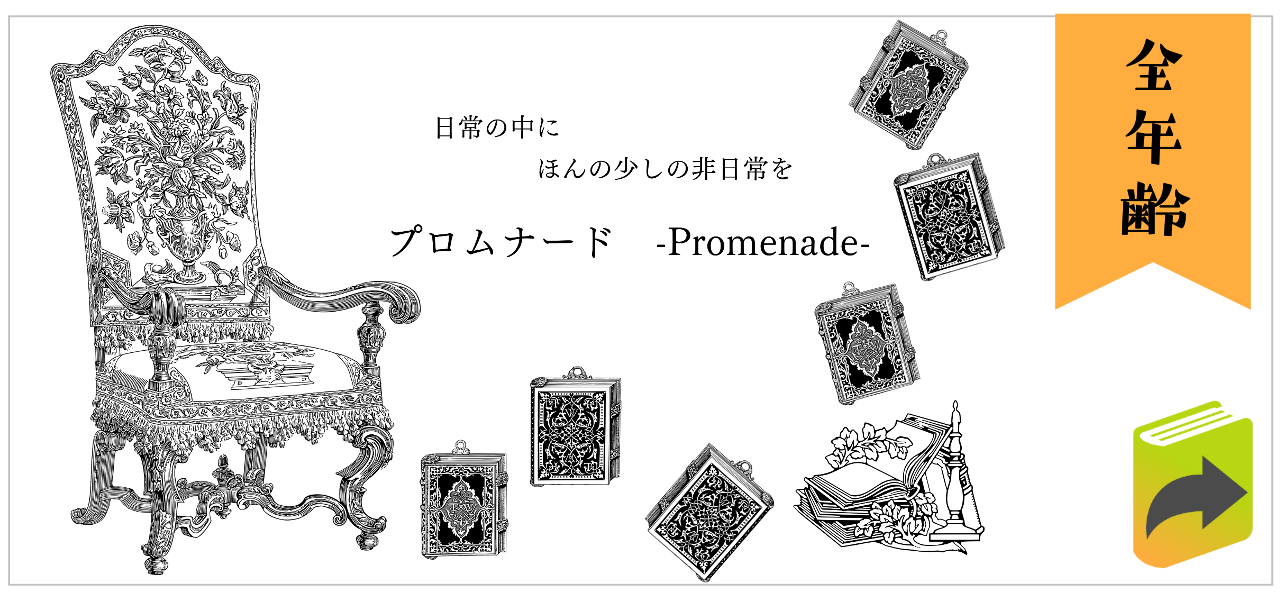読切「エディーナと精霊の守」
概要
2020年9月に頒布された星空ヱトランゼ様主催の「おはようの後に読む合同誌『エディーナと精霊の守』」参加作品となります。
》》寄稿詳細はこちら
エディーナと精霊の守
読み:えでぃーなとせいれいのもり
公開日:2020/09/21
ジャンル:ファンタジー
文字数:約5400字
読了時間:約7分
タグ:魔法/精霊/朝/主従
本編「エディーナと精霊の守」
群青で染まっていた世界に差し込んだ一筋の光。窓の向こうに見える山の稜線に沿って、黄金色の光が朝の訪れを伝えに来る。そのことにいち早く気づいたのは、朝を告げる鶏でも、木の葉に溜まった朝露でもなく、木枠で囲まれた窓からその様子を眺めていた一人の少年だった。
「もう、そんな時間か」
小さな鈴の音が鳴るような声。
可憐な響きをまとった音に迎えられるまま、朝日は空に手を伸ばしていく。
「これでいいだろう」
それは誰に向かって言っているのか。窓の外を見つめる少年の声は、小指の先ほど曇ったガラスに遮られて霧散する。きっと、かまわないのだろう。少年は何の問題もないという風にニコリと笑みを浮かべたまま、太陽が地上に光を届けていくのを見守っている。
たかが数分の出来事。
照れるように山に隠れていた太陽は、山の上に顔を半分出した途端、急に元気になったように頭上高く昇っていく。
「うぅーん」
少年の後方で、まだ夢の中にいる声が聞こえてくる。振り返ると、大判なシャツを一枚羽織っただけの女が枕を抱えて寝返りを打つところだった。
腰まで伸びた亜麻色の髪は波打つように柔らかく広がり、枕を抱きしめる手としなやかに伸びた二本の足は、心地よい夢の中を堪能するように幸せそうな表情を浮かべている。ちらり、と。少年は時計の針を確認した。
あと三十秒。時計の針が正しく時を刻んでいるなら、あと三十秒で惰眠を貪る女は飛び起きる羽目になる。
安寧の眠りが終焉を迎えるまであと二十秒。
「うぅーん」
女はまた、心地よさそうに寝返りをうち、枕を置き去りにして両手と両足を大の字に広げていた。
「あと十五秒」
少年の声が秒針を数えながら溜息を吐き出す。
「あと八秒」
めくれたシャツの隙間からのぞいた肌をかく寝相の悪さに、少年の目も冷ややかに落ち着いていく。それでも秒針だけは、時間を進めるのを止めはしない。あと三秒、静かに時は進んでいく。あと二秒、ふっと少年がイヤな笑みを見せた。あと、一秒。
「うわぁぁあぁぁあぁ」
耳元で盛大に鳴り始めた複数の目覚まし時計。もちろん、飛び起きるように上半身を起こした女は、奇襲でも受けたように狼狽えて周囲を見渡していた。
「なにっ、何事!?」
ベッドサイドに設けてある小さなテーブルの上から眼鏡を取ろうとしているらしい。まったく見当違いの場所に手を伸ばして、あたふたと眼鏡を探すその様子は、眠っているときの愛らしさをすべて放棄して混乱の様相をみせている。バサッ、ガシャン、ドタッ。およそ形容できる音を叩き出そうとしているのか、女はベッドサイドに乗っていたものを床に散らし、いまだ見つからない眼鏡の名前を呟き続けている。「はぁ」窓枠に腰かけていた少年は、呆れた息をひとつ吐いて、女の指先に目当てのものを触れさせた。
「まったく。昨日の夜、かけっぱなしで寝るからそうなるんだよ」
「てっテト!?」
眼鏡をかけるなり、今度は一向に鳴りやまない目覚まし時計たちを黙らせようと女は奮闘している。本当になりふり構っていないのか、誰もが羨む肢体を持ちながら、女は慌てた様子を隠そうともしない。静かに座っていれば可憐な花にも負けないのに、宝の持ち腐れとはこのことか。どうも、彼女は使いこなせないほどの不器用さを持ち合わせているらしい。
「これで精霊使いとか聞いてあきれるぜ」
テトと呼ばれた少年は、そろそろ耳が痛くなってきた現実を受け止めて、ふわりとその体を浮かせた。いつの間にか山から全身を現わしていた朝の光が、窓から部屋に差し込んでくる。その光を一身に受けたテトの背には半透明の羽が四枚ついていて、いつものように問題なくその体を浮かせていた。
人間と同じ五体を持ち、目と鼻と口を持つ。違うことと言えば、その背中で煌めく羽と少し先が尖った耳。俗に「精霊」と呼ばれる小さな少年は、これでいて百年を軽く超える年月を過ごしているらしい。
「テト。この目覚まし、どういうこと!?」
「時間通りに起きれたことをまずは感謝してほしいね」
「そんなところに浮んでないで、手伝ってよぉ」
「ふん。なんで俺様が」
空中で腕を組んで鼻を鳴らしたテトの眼下で、女は目覚ましに弄ばれる。止めても、止めても鳴りやまないのは、多分止め方が間違っているからなのだが、どうやらそれには気づいていないのだろう。なぜそうなっているのか、まるでわからないとでもいう風に、女は中途半端な格好のまま泣きべそをかいている。
「はぁ」
またひとつ。テトの口から重苦しいため息が零れ落ちた。
「お前を見てると、本当、自分が情けなくなるぜ」
宙に浮んだテトの指がパチンと小さな音を鳴らす。瞬間、すべての目覚まし時計は荒れ狂っていた騒音をぴたりと止め、窓から見える景色にふさわしい静かな朝の訪れを再現していた。
「た…っ…助かったぁ。ありがとう、テト。朝から目覚ましの襲来にどうしようかと思っちゃった」
へらへらと気の抜けた笑顔に説教の言葉も出てこない。テトは自分の何十倍もあるだろう女の前に降りてくると、その眼鏡に映り込むなり腰に手をあてて目を吊り上げた。
「おはよう、エディーナ」
口調と表情が合っていない。
朝くらい普通に起きられないのかと安直に目が物語っている。
「なんで、この、俺様が、お前を起こさなきゃならないんだよ。ったく、こんなやつと契約しちまった自分を呪いたいね」
ふんっと鼻を鳴らすその顔は、腰にあてていた手を組んで、ついでに足まで組んでいる。その左手首には小さな緑の宝石がついた金の輪がはめられていて、それはエディーナとの契約の証であることを示していた。
「んだよ、朝からニヤニヤ笑いやがって」
「へへ。テトと契約したのが夢じゃなかったんだなぁって、思ったらなんだか嬉しくて」
「馬鹿じゃねぇの」
頬を染めて照れたように笑うエディーナに反して、氷点下ともいえるテトの声が冷たい。朝日が差し込む穏やかな室内でこの光景は少しばかり異常だが、ようやく静かに朝を迎え始めた時間の中ではきっと何でも許されるだろう。しばらく互いを見つめ合っていた二人は、一台、遅刻した目覚まし時計の騒音に切り裂かれるまで、じっとそうしていた。
「ごっごめんね、テト。私、朝が苦手で」
「朝だけじゃねぇだろ」
「そっそうなの。あっあれ、髪を結ぶ紐、どこいったっけ?」
今度は自分で時計を鳴りやませたエディーナが、ベッドから足を降ろすなり、髪をかき上げながら室内を蹂躙する。見るも無残に散々した床。大抵は小難しい魔導書ばかりだが、本の虫といっても過言ではないエディーナの部屋には、それこそ棚が作れるほど膨大な量の本が散らかっている。
その中から小さな髪紐を探すなど、到底無理な話。
「エディーナ、落ち着け。おい、エディーナ」
「えっ、なっなに?」
歩くたびに本の山が崩れているのにエディーナは気付かないのか、テトが頭痛を抑えるように額に手をあててそれを止めるまでの間に、またひとつ部屋が壊滅状態に近付いていた。
「いいからそこに座れ、俺が探すからお前は動くな」
小さな指で命じられた場所は食卓の椅子。昨日まで本が積みあがっていたはずだが、今は何も乗っていない。大方、精霊の力で整理整頓が成されたのだろう。エディーナは素直にうなずいて、テトの命令に従った。
これでは、どちらが従者かわからない。
「大体、お前はなんでそう世話がやけるんだよ」
数秒とたたずに髪紐を浮遊させて運んできたテトの姿が、ついに怒りを通り越して呆れたような声をあげている。
「ごめんね、昔から本を読む以外に何も出来なくて」
「だろうな」
この部屋を見れば一目瞭然。しゅんとうなだれるエディーナを見下ろしながら、テトはエディーナの長い髪をひとつに束ねて、持って来たばかりの髪紐で縛り上げた。
「うわっ、すごい」
一瞬で髪型が整っていることに驚いたエディーナの声が感心したように震えている。
「精霊使いの自覚がまるでねぇな」
この程度のことは造作もない。人間が自分で出来る程度の力は魔力の消費にも値しないと、後ろから横を通って再び前まで浮遊してきたテトの雰囲気が物語っている。
「ったく、俺様と出会うまで一体どうやって生活してたんだよ」
「んー。なんとなく?」
「なんとなくで、よく生きてこれたよな。ほら、朝くらいしっかり食えよ」
「え?」
エディーナの前に突然置かれたのは、焼き色の美しいパンケーキ。ふわりと重なり合って、バターが溶けて滲んだ様子は、思わずごくりとノドが鳴る。
「テトが作ったの!?」
「他に誰が作るんだよ」
「食べていいの!?」
「他に誰が食べるんだよ」
これは夢じゃないだろうか。
実はまだ眠っていて、都合のよい夢を見ている可能性も否定できない。
「馬鹿なこと考えてないで、さっさと食え」
どうやら現実らしい頬の痛みに促されて、エディーナは躊躇しながらも、パンケーキを一口放り込んだ。
「ほいふぃい」
ふわふわと柔らかくて、しっとりと甘い。絶妙な焼き加減と厚みが、次から次へと口の中に運ばれるたびに、じゅわっと濃厚な香りを広げてくる。
こんなに幸せな朝があっていいのだろうか。
「今度はなんだ?」
テトはその眼鏡越しにキラキラと感激の目を向けられていることに気づいて、うっと顔を引きつらせた。見つめてくるエディーナの目が、室内を照らす朝の光を反射して朝露を浴びた葉のように綺麗な緑を宿している。
「え、本当にテトは綺麗だなぁと思って」
うっとりと熱のこもった視線に、テトの口角がピクリと跳ねあがる。
「あっあのね、変な意味じゃなくて、そっその」
「綺麗だと思うやつの羽を握り潰すか?」
「あれは、その、不可抗力というか」
「なにが不可抗力だよ。大体、精霊使いが精霊にからかわれて樹の上に登ったまま降りられなくなった挙句、俺様を捕まえて地上に転落するとかありえないだろ」
「捕まえたかったんじゃなくて、あまりに綺麗だったから、思わず腕を伸ばしたところでバランスを崩したといいますか」
「で、羽を修復する代わりに俺を使い魔にしたと」
「ちっ違うの。私、気が動転してて、治療しなくちゃって焦って力を発動させたら、どういうわけかこういうことに」
イヤな出来事を思い出したと言わんばかりに、テトの顔が氷点下に戻っている。腕についた緑の石の金色の輪。よく見ると、エディーナの右手、人差し指にもテトと同じ緑の石がついた金色の輪がはまっている。
契約の証。
精霊と契約を交わした特別な人間であることを意味する最上位魔法保持者の証明。
「ごっごめんね?」
パンっと両手を合わせて上目づかいで機嫌をうかがってくるエディーナの顔はもう見飽きた。昨日の出来事は夢でも嘘でもなく現実なのだから仕方がない。一晩たてば何事もなかった。などと、そんな本の中のような世界は訪れない。
「そう思うなら、早く契約解除の方法を習得するんだな」
「うっ」
痛いところをつかれたと、エディーナの顔が落胆に沈む。
自分でもどうしてこうなったのか、まるで見当がつかない。魔法学校での成績は下から数えた方が断然早く、ドジなところは昔から変わらない。本を読んでばかりで親しい友達もおらず、気づけば女盛りの適齢期。魔法もろくに扱えず、問題ばかり起こしてしまうせいで仕事がクビになった帰り道。
これでいったい何度目か。
気休めに立ち寄った図書館で借りた本を悪戯好きの精霊に奪われ、高い木の上に置き去りにされた。そこでテトの言うように一連の流れとなったわけだが、エディーナに言わせてみれば「自分が精霊と契約できるほどの上位魔法が使えるわけがない」という一言に尽きる。
それでも現実問題として契約の証が指にハマっていて、目の前に精霊がいるのだから疑いようはない。
「努力します」
落ち込んだ声でエディーナはテトに頭を下げていた。
「それにしても、部屋の掃除から朝ご飯までどうもありがとう」
「床はお前のせいで元通りだけどな」
言葉に詰まる。一言多い口さえなければ、悪くない契約だったかもしれないのにと、これから先の未来がしのばれる。
「あ、そうだ。どうしてこんな時間に目覚ましを?」
「何言ってんだよ。まだ寝ぼけてんのか?」
はぁっと、今度こそ完全に馬鹿にした声。
「今日からあのインチキくそ眼鏡のところで働くんだろ?」
その言葉にエディーナは、はっと顔をあげて時計に目をやった。いつの間に時計の針は周回していたのか、あれから軽く二十分は経過しようとしている。
「サフィラス先生!?」
王立魔法図書館の館長サフィラス・ドルセモア。
昨日テトと契約した際に偶然遭遇したことがきっかけとなり、エディーナの新しい仕事先は無事に決まった。テトはよく知っているようだが、初見のエディーナはサフィラスがどんな人物かもよく知らない。ただ、テトが「あいつは怒らせると怖いからな」と言うのだから、初日から遅刻だけは避けたいところだ。
呑気に座っている場合じゃないと、エディーナは椅子から立ち上がって、足元に積みあがっていた本の塔をまたひとつ盛大に倒していた。
鈴の音の笑い声が天井の方から降り落ちてくる。
「テト、笑ってないで手伝ってよぉ」
朝の支度は慌ただしく本の山に埋もれていくだろう。小さな精霊と少しドジな人間。奇妙な組み合わせが巻き起こす日常は、きっと予測できない未来に満ちているに違いない。
「エディーナ、行くぞ」
玄関の扉を開けたテトを追いかけてエディーナも部屋の外へと飛び出していく。
外は晴天。すっかり空を堪能している太陽の光は、特別な青を広げながらエディーナの影を新しい道へ連れ出していった。
(完)

プロムナードとは
遊歩・散歩を意味するプロムナード。「日常の中にほんの少しの非日常を」というコンセプトを元に、短く仕上げた物語たちのこと。皐月うしこオリジナルの短編小説置き場。
※文字数については各投稿サイトごとに異なる場合があります。
※読了時間については、1分あたり約750文字で計算しています。